
21世紀COEプログラム、大分子複雑系未踏化学
山本 嘉則

理学研究科および工学研究科の化学系が21世紀COEプログラムに採択されたことは誠に祝着に存じますとともに、一方では東北大の化学系の今までの実績を考えると日本での化学系のトップ10の中に入るのはある意味では当然であると思います。むしろ重要なのは、過去の歴史よりはこれからどの様な実績をあげどの様なstatusを日本国内および世界において築いていくかでしょう。このプログラムを成功させ次のプログラムにつなぐためにも、現役およびOBの諸先生方、次の時代を担う若き研究者および学生諸君の御協力と御尽力をお願いする次第です。
我々化学系のCOEプログラムは表題にも記しました様に「大分子複雑系」を研究のテーマとします。図1に示した様に、化学が取り組むのは大体0.1nmから100nmに至るまでのサイズの分子です。これより小さい物は物理の分野ですし、大きい物は生物の分野と云えます。我々が日頃取扱う通常の分子は大体0.1nmから1nm程度までですし、10nm-100nmのものは通常は高分子化合物です。ところが、1nm-10nmの領域の分子(大分子)は、今までに本格的に化学者が取り組んでこなかった領域です。高分子はこれよりも大きい分子ですが基本的にはくり返し構造から成っておりユニット分子は比較的単純な構造をしています。大分子は、極めて巨大な分子でしかも単純な構造のくり返しからできているのではなく、それ自身が極めて複雑な構造をもっており、最近の機器の発達により構造の明確化や精製・単離が行えるようになり、化学者の前に登場して来だしたと云えるでしょう。また、単一分子から成るのではなく、分子集合体として大分子を形成し複雑な構造をもち、新規で有用な機能を発現する物質群もあります。この様な大分子複雑系を研究対象とし、それ等の機能発現や機構、合成、材料への応用、バイオ関連科学への展開を狙うのが、東北大化学系COEの目的であります。
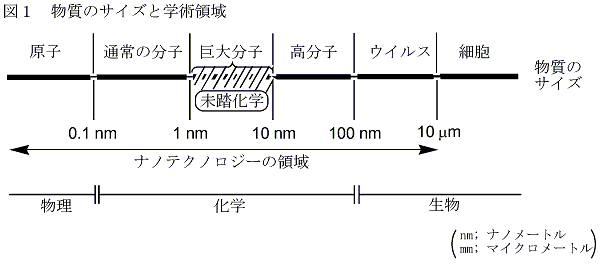
教育に関してどのような施策をとれば、本拠点を真に世界のトップレベルに到達させることができるのでしょうか。具体的な取り組みとして、外国人助教授による英語での授業および国際学会でのプレゼンテーションの訓練、欧米の一流化学教室への学生及び若手教官の派遣、理学及び工学研究科のカリキュラムの相互乗り入れ、博士課程の優秀な学生への経済的支援などを行っています。博士課程(後期)の学生は全員なんらかのサポートを受け、上位のものは仙台での生活をやっていける程度の支援をうけられるようになっています。特に、英語の問題は重要で、日本人の国際学会での発表はずいぶん上手になってきたと思いますが、アジアの中でもまだまだ我々の英語でのスピーチ力は弱いと思います。
研究に関してどの様な施策をとれば本拠点を世界のトップにもっていけるでしょうか。これは各研究者に実績を上げて頂くしかなく、特別に有効な策はないかもしれませんが、サポート策として次の手だてを打っています。"Giant Molecules and Complex Systems,"に関する国際会議を仙台で開催(年数回)する、欧米の一流研究者のサバティカルを仙台で受け入れる、研究推進のためポストドクターを採用する、研究費の重点的配分を行う、などをすでにスタートさせています。これ等の施策により、この5年間で東北大学化学系から世界をリードする研究成果の発信が行えるとともに、10数年後には次代を担う若者が仙台の地から巣立っていくことを切に願うものです。同窓会会員の諸氏で、これ等施策以外に良いアイデアをお持ちの方はEメールで山本まで御連絡下さればありがたく存じますし、参考にさせて頂きたく存じます。(e-mail: yoshi@yamamoto1.chem.tohoku.ac.jp)また、化学系COEプログラムの詳細と経過は次のweb siteで見ることが出来ます(URL: http://www.chem.tohoku.ac.jp/COE/index.html)。あるいは東北大学あるいは化学教室のホームページにもリンクしていますので、そちらからでもアクセスできます。本プログラムの成否は、理及び工の化学系の構成員の皆様が各人でトップを目指して切磋琢磨して頂くかどうかに大きく依存しています。よろしくお願いします。最後に、本プログラム申請時には先輩及び現役の先生方に大変御協力頂いたことを、この場を借りて御礼申し上げます。
真島利行先生の最新中等化学教科書
大森 巍(昭和35年卒)
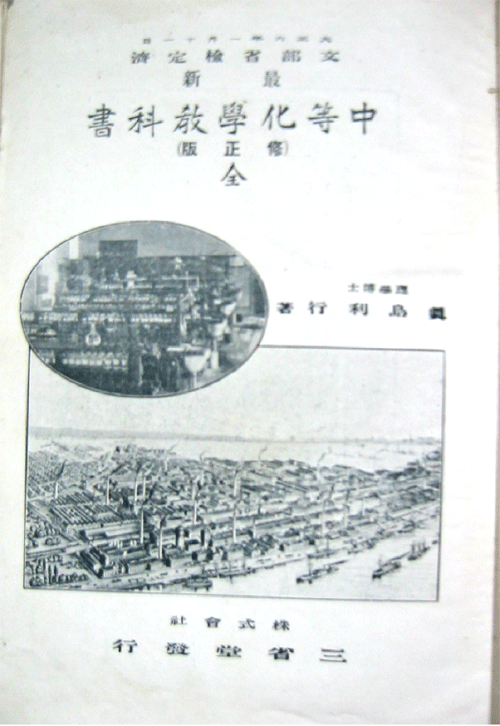
郷里の蔵を整理していたら、叔父が使っていた真島利行先生の書かれた旧制中学校の化学の教科書「文部省検定済最新中等化学教科書」が出て来た。発行は大正五年第5版となっているが、定価90銭のところ、大正9年度臨時定価1円53銭と訂正されている。叔父はこの年4年生であったから、その頃使ったものであろう。
扉の写真には化学実験室内景として、東北帝国大学化学教室が写っている。教科書には、先ず「緒言」が以下のように書かれている(原文は縦書き)。
**********
緒言
抑自然科學現今の發達は甚だ顯著にして、其學理と應用とが、人類の思想と生活とに影響せるところ、極めて大なるものあり。故に其概略を知得するは、吾人の常識涵養上缺べからざることに屬す。中等教育に於て物理學・博物學等と相並びて化學を課する所以、蓋し亦茲に存すべし。況や近時歐州の大戰は化學の重要なることを一層質實に表明したるに於ておや。本書は専ら此中等教育の目的に副はんがために改正細目に遵ひて編纂したるものにして、特に左の諸点に注意せり。
一、物質の記載は日常吾人の親炙するものより入りて、徐に他に及ぶことを主眼とし、且つ總括しうる事項は成るべく之を一章内に集録する方針を以て一貫し、事實の連絡、記事の統一を圖れり。例ば第五章に於て鹽素・鹽化水素を述ぶるに當り、先づ食鹽より説きたるが如し。金屬の部に於て各元素に就き、鹽類の實用大なるときは之を先に記し元素の應用多きときは之より始め、有機化合物は先づ動植物より直に得らるゝ物質を説き、次に之より化學的に製せらるゝものに及べること皆同じ理由に基く。また各物質に就きては、其應用の途を説き且つ日新の事實を傳へんことを期せり。
一、化學理論を理解し易く記載するは、其歴史的発達の順序に従うに在りと信ずるを以て、大体に於て此方針に従ひ、原子・分子説の如きも原子量・分子量に先て之を記せり。
また化學式は金屬元素又は之に相当する基を先づ書する方式に則れり。少許の利便により大勢に抗するの益なきを思へばなり。
一、圖畫は特に之を精選して挿入せるもの、巻頭及び表紙裏及圖版等を合して百七十 餘に達せり。教師は事情の許す限り實物及び實験を示し、且つ簡易なる實験は生徒にも之を行はせしむべきなれども、時間及び設備の都合により意の如くならざることあるべし。斯る場合にも生徒は此圖によりて推察し得べく、教授上の便益少からざるべし。また勉めて工場の圖を収め、化學と其工業との間に密接なる関係あることを知らしめ、また大発見者等の肖像を掲げ、生徒の興味並に志気を喚起せんことを期せり。
一、巻尾に附録として問題を与へ、主要なる事項を回臆せしめ、また学習したる智識を応用する慣習を養はしめんことを期せり。
本書は多数の圖畫を有し且つ説明も稍々周到なるにも拘はらず其頁数三百十余に止まり、又比較的重要ならざること、及び専ら應用に屬することは五号活字にて記述せるを以て、此等を適宜に取捨すれば、第一部及び第二部を第四学年にて、第三部及び第四部を第五学年にて優に教授し得べし。但し第五部に於ける溶液論は生徒の進度に応じ、或は之を第二部の終わりに講ずるも妨げなし。第三部に至りて上欄にイオン式による反應式を記し、且つイオンの色等を表示したれば斯る場合にも便利あるべく、また後来復習に際して有用なるべし。問題は適当に之を利用あらんことを希望す。
巳に多數良好なる教科書世に行はるゝをも顧みず、茲に敢て本書を上梓する所以は、中等教育の目的に適切なる多少の特色を具ふるものありと信ずればなり。然れども著者の浅學短才なる、或は教材の撰擇、布置其當を失し、或は解説の不備なる点なきに非るべし。冀くは大方の示教に吝なるなからんことを。
大正五年九月 著者識
**********
教科書の中身を先ず目次から見ると、次のようになっている
最新中等化学教科書目次
第一部 化学緒論及び非金屬の化學(其一)
第一章 空気及び其成分
空気・燃焼・酸素・窒素・アルゴン・空気の成分
第二章 水
水の性質・天然水・水素・水の組成
第三章 化合物及び分解
化合物及び元素・質量不変の定律・定比例の定律
第四章 炭素及び其化合物
炭素・無水炭酸又二酸化炭素・酸化炭素・ 倍数比例の定律
第五章 食鹽 鹽素及び鹽酸
食鹽・鹽素・鹽化水素及び其組成
第六章 アムモニア 鹽化アムモニウム
アムモニア及び其組成・酸・鹽基及び鹽・鹽化アムモニウム・可逆反應
第七章 原子量及び分子量
気体の通性及び気体反應の定律・アボガドロの假説及び原子説・分子量及び原子量・元素の原子記号・化學式・反應式
第八章 炭素の簡單なる化合物
炭化水素・火焔・シヤン化水素
第九章 原子價構造式及び元素の當量
第二部 非金属の化學(其二)
第十章 ハロゲン元素
弗素・塩素・臭素・沃素・ハロゲン元素と水素との化合物・ハロゲン化物
第十一章 窒素の酸素化合物
硝酸・窒素の酸化物
第十二章 酸素屬元素
硫黄・硫化物・硫黄の酸素化合物・酸素の同素體及び過酸化水素
第十三章 珪素及び硼素
珪素及び其化合物・硼素
第十四章 窒素族元素
燐・砒素・アンチモン
第十五章 非金屬及び金屬元素
第三部 金屬及び元素の週期律
第十六章 アルカリ金屬 附アムモニウム
ナトリウム・カリウム・アムモニウム
第十七章 アルカリ土類金屬
カルシウム・バリウム及びストロンチウム
第十八章 マグネシウム及び亞鉛 附カドミウム
第十九章 土類金屬 アルミニウム
第二十章 錫・鉛及び蒼鉛
第二十一章 クロム及びマンガン
第二十二章 鐵屬元素
鐵・鐵の化合物・ニッケル及びコバル
第二十三章 水銀・銅・銀・金及び白金
第二十四章 金屬概論
第二十五章 元素の週期律
アルゴン族元素及びラヂウム
第四部 有機化合物
第二十六章 有機化合物及び其分析
第二十七章 炭水化物
澱粉及び其加水分解・蔗糖及び乳糖・セルローズ及び其應用
第二十八章 酒類の醸造・アルコホル
酒及びアルコホル・アルコホルより製せらるゝ二三の化合物
第二十九章 木材乾溜及び其果成物
メチルアルコホル及び酢酸・それらより製せらるゝ重要化合物
第三十章 有機化合物の構造式及び其分類
第三十一章 脂肪・脂肪油及び臘 附果實等の酸
第三十二章 炭化水素及び石油
第三十三章 石炭の乾溜
第三十四章 芳香屬炭化水素及び其誘導體
芳香屬炭化水素・重要なる芳香屬化合物の数種・人造色素概要
第三十五章 精油類・樟腦・弾性ゴム
第三十六章 アルカロイド
第三十七章 蛋白質類
第三十八章 動物及び植物の榮養
第五部 溶液論
第三十九章 溶液 附分子量の測定
第四十章 イオン
電解・電離・酸・鹽基及び鹽・イオンの置換
**********
このように現在の高等学校の化学の教科書と比べると、扱っている元素、化合物の数は多く、また内容も多岐にわたっている。
実際に教科書の中身を見ると、例えば「化学変化」とは、「物質が変化して全く異なれる性質の物質となり、此原因止むも原物質に復することなき深大なる変化を化學的変化と云ふ。燃焼の他、鐵鉱より鐵を製出すること米より酒を醸すことの如き、皆化學的変化に他ならず。化學は専ら化學的変化を研究する學なり。」とあり、傍点の語句には英語のルビまでついている。
真島先生が研究されていた漆についても、「漆は漆樹の樹皮より採取せる汁液にして、一種の酸化酵素を有し、空気中にては直に酸化して黒色となる。其主成分は芳香屬化合物にして、沒食子酸と稍似たる点あるものなり。」と記されている。
巻末には周期表が掲載されているが、小川正孝先生のニッポニウムはなく、43番元素のところは空欄になっている。
教科書を読んでいて気付いた事は、各論はかなり詳しく記述されているが、分離分析化学に関する記述が殆んどないことであった。1902年にはA. A. Noyes が系統的金属イオン分析法を発表しているし、また祖父が医学校で使ったと思われる教科書(J. Attfield, “Chemistry”, (1873))にも金属イオンの硫化物沈殿分離法が既に載っていることから、中学校の教科書にも取り入れられていてもよいのではと思い、国会図書館にある当時の中等化学教科書3冊についても調べたが、いずれも分離分析法に関する記述は、真島先生の教科書と同様であった。分離分析法は、旧制高校、大学における課題と考えられていたのだろうか。
貴重な資料であるから、製本して化学教室に寄贈したいと考えている。興味ある方はご覧いただければ幸いである。