
停年退官に当たって、ー始と終ー

宮仕 勉
私は昭和33年東北大学に入学しましたので、今年で45年が過ぎたことになりますが、約3年間の企業生活と4年間の留学生活がありますので、30数年 間化学教室にお世話になった事になります。この間、私は野副先生、向井先生はもとより、多くの先輩、同僚、後輩に恵まれ、無事退官できたことを大変幸せであったと思っております。
入学時の教養部はまだ三神峯にあり一年の前期を三神峯で過ごした後、後期からまだ米軍兵舎の残る川内で教養課程を過ごしてました。化学科への進学決定後の配属は予定どうりトロポロン化学の研究をめざし野副先生の研究室を選び、向井先生の直接指導を受けることになります。トロポロン化学の研究を期待していた私には卒論最初のテーマが活性メチレンを持つトロピリデン誘導体のアシル化反応であった事は予期せぬ事でした。しかし、幸いにもこの研究が日本化学会欧文誌に掲載され、私の最初の論文となりました。4年生後半に研究テーマが突然有機光化学に変更された事も予期せぬ事でした。有機光化学は当時欧米では盛んになりつつある研究ではありましたが、日本では向井先生が先駆者となる有機化学の新しい研究分野でありました。何の知識も持たないままに、向井先生の指導のもと様々な七員環化合物の光化学反応を行いましたが、昭和36年当時はNMRは無く生成物の構造決定どころか生成物の検出さえも困難を極めたことを記憶してます。しかし、昭和38年大学院進学後、NMRや薄層クロマトの実験手法が導入され状況が一変しました。実験のたびごとに新しい結果が得られ、実験の楽しさを満喫したものです。また光化学の研究過程で熱反応の面白さに初めて出会ったのもこの時期でした。これらの結果をもとに昭和43年 「二、三の不飽和七員環系化合物の光化学反応」のタイトルで学位を取得できたのは大きな喜びでした。以後、成果等は最終講義で話しましたように、昭和 44年末からの助手時代、昭和55年からの附属光エネルギー化学実験施設の助教授時代、昭和62年から平成15年の教授時代を通して光化学や反応機構を ベースにした研究を展開してきました。研究の始での光化学との遭遇が運命的だったことになります。研究生活の終を経験したいま、真っ先に思い出されるこ とは、どの研究にもドラマがあったことであり、決して無味乾燥なものでは無かったということです。偶然の発見の歓喜、見事なまでの失敗、ライバル研究者 との競争等数々のドラマが思い出されます。
猛威をふるって大学紛争を経験していない私にとって、化学教室生活の始と終での経験で最も印象深いことは、教養部の廃止に始まる大学院重点化、独立法人化のいわゆる大学改革の動きです。これらの三つの改革に確固たる整合性が認められないことと法人化には必ずしも純なるものが認められないのは残念に思います。地震に例えても、これらの改革がマグマの変動によるものではなく人工地震によることも残念でなりません。もし、本震が法人化であればその余震が今後しばらく続くことは充分に予想できます。後進の研究と教育活動に支障がでないよう、知恵と私欲を排した協力により改革をすすめることが大切と考えま す。
化学同窓会会員の皆様のますますのご健勝とご活躍、化学専攻のますますの発展を祈念してやみません。
宮仕先生の思い出
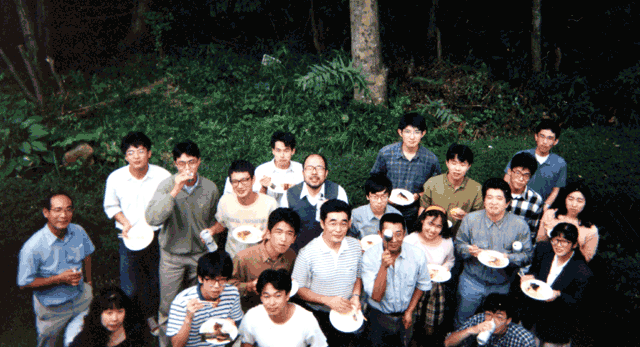
高崎俊彦(平成2年卒)
宮仕先生には研究室配属から博士課程終了まで6年間お世話になりました。その間、研究に対する態度や研究方法はもとより、様々なことでご指導を賜りました。ここに改めて感謝申し上げます。
私が宮仕研究室に配属した時、先生は教授になられて3年目ぐらいで、最初とても厳しそうな印象でした。実際研究に関しては非常に厳格で、研究相談会や修士、博士課程事前審査では何度も厳しい質問を受け、立ち往生した記憶があります。また、実験方法についても我々の知らない豊富な知識を持っておられ、例えばNMRチューブの洗浄は水蒸気を用いる方法がいちばんいいと教えて頂いたこともありました。先生から研究に関して教わったことは非常にたくさんあるのですが、いちばん大切なことは、単なる技術や知識ではなく、どのように研究を進めるのか、どうしたら問題を解決できるのかということについて考える力を付けて下さったことではないかと思っております。
一方、宮仕先生のお話をする上で"酒"をはずすことはできません。当時研究室の行事は、花見に始まり春の旅行(1泊)・かつおの会(かつおのたたきで飲む)・野副杯関連・夏のキャンプ(1泊)・院試打ち上げ・芋煮会・忘年会・新年会・送別会(1泊)・その他適宜と、飲み会が目白押しで、私のような悪学生にはまさに天国のような研究室でした。類は友を呼ぶというか、毎年のように酒好きの学生が配属され、セミナー室で飲んでいると他の研究室からも人が集まり、そのあと国分町に繰り出しては毎回3次会4次会と最後まで先生にお付き合いしていただきました。春の旅行は宮仕先生の意向で毎回電車旅行だったのですが、当然電車に乗ったとたんにビールが入り、ほろ酔い気分で途中下車してつまみを買って近くの河岸で先生と飲んでいたこともしばしばでした。宮仕先生もお酒はお好きだと思っておりますが、かなり我々が度を越していたことも多分にあったと思います。それでも最後までお付き合いいただき、いろいろな話をしてくださったことは感謝の念に耐えません。
また、先生のご趣味は多岐にわたっておりますが、その中で"釣り"は別格と思われます。仕掛けの水中での挙動を確かめるべくお風呂の中で"実験"した等の話をよくされておられ、化学と同様(以上?)の熱意で釣りに取り組んでいたようであります。残念ながら一度しか釣りにご一緒できなかったのですが、ぜひまたご相伴させてください。
他にも思い出はたくさんあるのですが書き切れないのが残念です。先生の益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
宮仕先生の思いで
帝人ファーマ株式会社勤務
羽里 篤夫
平成15年3月。一人の男がユニフォームを脱いだ。
皆に尊敬され愛され、大の長嶋ファンだった宮仕先生・・・
その月の7日には退官記念行事が行われ、私もその中にいた。博士課程修了から20数年たち、自分が行ってきたテーマはすでに記憶の奥底に沈んでしまっていたが、先生の記念講演で鮮やかによみがえってきた。「オキシコープ転位」だったんだと。昭和49年、当時モラトリアム人間だった私は有機化学が取っつきやすいというそれだけの理由で、向井研(有機第一講座)を選んだ。配属されたとき「8月からは帰ってくる宮仕君についてもらう」と向井先生に言われ、そのときが「宮仕先生」の名前との初めての出会いだった。講座内での評判といえば、「新進気鋭」、「講座の期待の星」、「厳しい」・・・
昭和49年8月、宮仕先生と初めてお会いした。戦々恐々としていた私は、その柔和で温かい人柄に触れ、またまたお酒を飲まれても変わらない性格、高校の先輩でもあったこともありほっとしたことを覚えている。
「来年4月からは俺のテーマをやってもらうから宜しく頼むぞ」・・・
その年の10月、先生が大ファンの長嶋茂雄が引退した。その時の先生の寂しそうな表情は今でも忘れることができない。そして昭和50年、先生は宮仕グループを集め、「今年の俺のキャッチフレーズは<クリーンケミストリー>でいくからな」・・・ (今の言葉で言えばパクリでしょうか)
その年、長嶋茂雄の監督としてのシーズンが始まる。しかし<クリーン・ベースボール>と名付けてスタートした巨人軍の成績は、予想を遥かに越える散々なものであった。だが、<クリーンケミストリー>はその全貌を表していく。
それは、反応におけるfalse-positive、false-negativeを徹底的に排除するというものであり、酒の席でもその重要性を熱っぽく語られた。先生は実験の準備と使用試薬、溶媒の選択にとくに注意を払うよう指示され、そのためのガラス器具を自ら設計された。たとえば水銀シール付の反応用真空ライン(当然アルゴン使用)無水溶媒蒸留装置(無水化するための脱水剤選択ノウハウ含む)カラム分離不能な実験使用化合物の分離のためのスピニングバンド設計(見事分離成功) など結果に影響する不安定要因をできる限り排除するというものであり、当時の向井研にも目新しい実験技術であったと記憶している。実験を行うためにはその設計と準備がいかに大事かという基本的姿勢を宮仕先生からお教えいただき、現在もなお私の財産になっている。この<クリーンケミストリー>の教えがあったからこそ、私が宮仕先生のライフワークの「コープ転移」研究に貢献できたと今でも思っている。
退官記念行事の際に先生はこんな言葉をおっしゃった。
「いままでの人生の大半を研究に注いできた。これからは自分の時間を自分のために使いたい」・・・
まずは釣り三昧らしい。
「反応は起こるべくして起こる」
平野 誉(昭和61年卒)
電気通信大学勤務
宮仕勉先生、ご退官おめでとうございます。
私の大切な先生、宮仕先生は軽はずみなことの多い私に対して、科学者としても、教育者としても、人間としても辛抱強く多くのことを教えていただきました。時には励まし、時には誤りを正していただき、先生への感謝の念は尽きません。ご退官記念に際し、私の思い出であり、これからの道筋としても大切な先生から教えの一部を紹介させていただきます。この思いを同窓会の皆様と共有できれば幸いです。
タイトルにあります「反応は起こるべくして起こる」、この言葉は化学者にとって当たり前のことだと思います。しかし、この言葉は時に戒めであり、時に励ましでもあります。大学院生の時、経験の少ない私は光反応により変な(すでに矛盾します)生成物を単離しました。場面は化学棟3階の教授室につながるセミナー室です。私は得られた生成物が予想に反したものだったので、「これは異常なおもしろい反応が起きた」のだと考え、喜んで自慢げに先輩と議論していました。その話を横で聞いていた宮仕先生が一言「反応は起こるべくして起こる」、ぐさりとアドバイスしてくれました。先生には、私が放った「異常な反応」という表現、そういう判断を下した私の浅はかな考えに、すぐさま誤りを正そうとしていただいたのだと思います。化学者として、おもしろい反応を見つけて感動するのは良いのですが、それを異常なものとして自慢したり、そこで考えるのをやめるのは明らかにおかしいですので、当然の正さなければいけません。「反応は起こるべくして起こる」のですから、おもしろい反応には、そうさせる何かの要因が必ずあるわけです。反応1つ1つが自然に従っている。謙虚に自然を考えることから科学が始まり、発見があります。このことの大切さを教えていただきました。その後、私も研究室を持ち、学生さんが実験しておもしろい結果を持ってきます。言葉でつい「変な反応だね」と言ってしまうのですが、すぐさま宮仕先生の顔が浮かびます。そして、なるべく客観的に、論理的に起こった反応を考え、学生さんと一緒に議論しています。私も少し進歩できたでしょうか?また、普段のことですが、アイディアが浮かび、分子設計したおもしろい分子を作ろうと考えた時、多少難しそうでもまた宮仕先生の顔が浮かび、「反応は起こるべくして起こる」。ですから良く考えればできるはずと考え取り組みます。まさに化学者ならではの前向き(ポジティブ)な考えで、達成できた分子が少しずつ増えています。
このように、私は小さなことですぐ有頂天になってしまうことが多いせいか、宮仕先生から一言いただいてしまうのかもしれません。あのキャンプの時もそうでした。私の大学院時代は、夏のロックアウト(今もあるのでしょうか?)の時に研究室でキャンプに出かけました。ご存知の通り先生は釣りの名人です。先生の情熱には比べ物になりませんが私も釣りが好きなので、ご一緒させていただきました。場面は三陸の岩場です。きれいな海に糸を垂れ、先生には缶詰のコーン(釣りえさを触った手の汚れが口に入らないよう、スプーンで食べられる良い食料です(先生のお教えの一つ))をご馳走になりつつ釣っていますと、10cm程のネウ(アイナメ)が私ばかりに釣れました。私が喜んで2-3匹ほど釣った頃です、宮仕先生に大きな当たり。そして60cm程のネウが釣り上がりました。先生には、この時また一言いただいたように思います。大きな針を使い、じっくり待って大物を釣る。しっかりとしたフルペーパーをまとめる先生の姿と共に、論文書きの時に思い出す風景です。
こんな私も授業を持つようになり、心がけることは若者に夢を持ってもらうこと。化学のおもしろさ、すばらしさを伝えることです。そんな時に見本とする理想の授業の一つに宮仕先生の授業があります。それは「ハメット則」と「重水素効果」を教えていただいた授業です。恥ずかしながら、私は櫻井先生の有機化学の授業をぎりぎりで修めておりましたが、それに続くアドバンスな内容で、宮仕先生の授業を受けました。きれいな「ハメット則」と「重水素効果」の法則性によって有機化学がすごく論理的なものに変わり、目の覚める思いだったのを記憶しています。先生は落ち着いた面持ちで授業されていたと思いますが、本当にたくさんの反応例(しかもおもしろい反応)を示しながらじっくり説明され、先生の胸の中の情熱が伝わってきました。先生のこの授業のための膨大な資料を思うと、私はまだまだ勉強が必要です。このような理想、目標を示していただいたき、私は本当に幸せ者です。
学会でお会いするたびに先生から温かいアドバイスをいただき、私の大きな励みとなっております。私の博士論文の研究で、先生の先生に当たるBerson教授から宮仕先生がお褒めに預かったことを喜んで教えていただいた時も、私も心からうれしかったです。などなど先生の温かい懐に甘えすぎていたかもしれません。これからは、私の方が若者に熱く伝えていくべき時代となり、がんばりたいと思いを新たにしています。でもやはり、先生にはこれからも釣りと共に情熱を持ちつづけているでしょう化学への気持ちによって、アドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。