勲二等瑞宝章を受章して
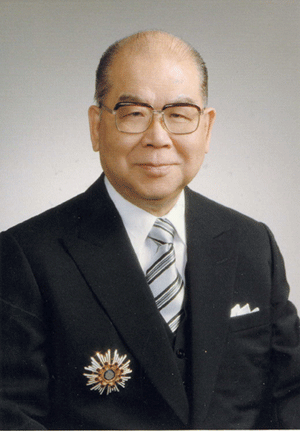
東北大学名誉教授 櫻井英樹
丁度1年前になるが、平成14年度秋の叙勲で勲二等瑞宝章を受賞する光栄に浴した。この秋から叙勲制度が変わったので旧制度の秋の授章としては最後のものとなる。
業績があって一定の年齢になったら、自然に叙勲ということになるのかと思っていた。若いときには気がつかなかったが、そうではないのである。業績調書というのを作成して提出するということになるのだそうである。業績リストや兼職記録などは勿論、過去に授章した内外の賞やメダルなどについてその意義、過去の受賞者リストなど詳細な調書が必要のようであって、その作成に当たられた吉良満夫教授と理学部事務部人事係の皆様にはその労苦に感謝申し上げたい。
伝達式は平成14年11月7日に皇居で行われた。当日朝、家内とともに坂下門から参内した。前回参内したのは恩賜賞・日本学士院賞受賞の午餐にお招きいただいたときで晩春であった。そのときの皇居の庭には花が咲き乱れて美しかったが、紅葉の始まりかけている秋の風情も、少し曇ってはいたがしっとりと落ち着いたものであった。
表御座所北棟の西車寄から入り、回廊を通って長和殿春秋の間に案内され暫時待機した。勲二等各賞は内閣総理大臣から伝達されるのであるが、その日は国会の都合で小泉首相は出席されず、福田内閣官房長官から石橋の間で伝達されることになった。その後一同そろって豊明殿にすすみ、天皇陛下のご拝謁を賜ったのである。天皇陛下は手術を控えておられ、ご健康が心配されたが、しっかりとした足取りで歩み寄られ、一人一人に声をおかけになった。なお、無事手術を終えられた陛下の、復帰後最初のご公務がその翌年、つまり今年の3月の日本化学会125周年記念行事への行幸であった。そのときも記念式典およびレセプションでお元気なお姿に接することができた。
来し方を振り返ってみるに、須臾の間のようにも思えるが、やはり長い年月であった。一生懸命働いてきたとも思うが、自分としては好きな化学に没頭できた幸福な毎日であった。なかんずく東北大学理学部に赴任してきた1969年以来、SendaiのSakurai研をSi化学のメッカにしようと研究に精進してきた研究室の職員、大学院生、学生の諸君に支えられて楽しい毎日であった。
はじめは研究室も火の車で、やりくりに苦労したし、分留塔など実験道具も自作しなければならなかった。試薬などもほとんどすべて、簡単な出発原料から合成するので、今日のように何でも注文すれば持って来るというのとは雲泥の差であった。しかしそれは苦労でも何でもなく、充実した日夜であった。やがて研究室も整備され、1987年には有機ケイ素材料化学実験施設が開設されて、メッカであるかどうかは別として、仙台は確実に有機ケイ素化学の世界的中心となっていった。
25年あまり化学教室にお世話になり、150人ほどの卒業生を送り出して、1995年春定年退官となった。その間、先輩、同僚の皆様にはいろいろ公私にわたってご援助いただいたし、家内や子供たちに励まされてきた。
叙勲に際して内示があった。賞を受けるかどうかということである。そのとき、正直言って、もうその年になったのかという思いがよぎった。こういう形で総括されるのかという思いもあった。それでも受賞を皆さんに祝っていただいてうれしく思っている。卒業生の諸君を中心に東京で、現在の勤務先の(財)みやぎ産業振興機構・(株)テクノプラザみやぎ・発明協会東北支部の皆さんを中心に仙台で、祝いの会を開いていただいたし、大勢の方々からお祝辞をいただいたりして久闊を叙する機会ともなった。
いつの間にか21世紀となり、大学も独立法人化とかで大きな変革期を迎えつつある。変わらないのは同窓会の人のつながりである。皆様のご多幸を祈り、同窓会の発展を祈って小文を措きたい。
受賞寄稿
平成15年 春 叙勲
叙勲に関して
宇野原信行(昭和23年卒)

上題に就いて同窓会幹部から寄稿依頼が有ったので、思い付く儘に2,3述べて見て、少しでも参考になれば幸です。
理学部化学では今迄に多くの方が叙勲されて来たにも拘らず何故に私がマークされたのか良く分りませんが、恐らく私学関係からは叙勲者の数が非常に少なく、珍しいからかも知れない。或いは又、まさかと思はれる宇野原の意外性が問はれているか、更に場合に依っては両方が複合しているかとも考へられたが、実際に小生自身も昨年の8月頃に思いも寄らず突然に電話で叙勲の話しが有った時は吃驚りした次第である。
世間では熱心に叙勲運動される人が可成り有ると新聞にも記されている由、効果が有るのか無いのか疑問と思わざるを得ない。何故なら私の経験では途中で学部と本部その上に文部科学省等の厳重・緻密な審査があり、過去にも現在も一切の私情は差し挟み得ない現実がある。
併し、来季からは勲章の等級(数字)が無くなると聞く、これ等には大反対の人々が居る。その言に依れば競争心が薄まり、世の中は競い合ってこそ始めて進歩の跡が見られて来ると云はれるのに、これが無ければ余りにも味気がなく無意味と言う。この意見には既に充分の業績が有り自信を持つ人に数多い。然し逆に数字で表現する等級差が国民に着くのは刺刺しく殺伐であると強く反対する人々の方にポイントが置かれた様であるが、世の中は総べて心からの全員一致が殆ど無い。
何れにしても、この制度は大凡70〜80才の人が対称になっているから、人生最后の総決算の印の様な気がしないでもない。尤も80才以降も元気矍鑠、世の為に人の為に更にもう一働きする方が居られるから、一概には断ぜられない。兎も角、平均年齢を78とすれば其の前後まで生きれてこそ受けれる制度で、これだけが万人に共通する唯一の条件となる(我が国では死亡叙勲も有るが)。 来季からは、一般部門の口も、即ち門戸を拡大すると聞く、尚、勲章の種類の旭日章は1875年から発足し、瑞宝章が其の後、1888年に総べての勲位の各階等に加はったが、宝冠章は女性が対称で、何れも国および地方公共団体等の公務に或いは夫れ以外の各界各層の仕事に従事し功労の有った者とされ、この栄典制度は今後も継続されて行くが、勲六等まで約70才以上の方々の1000人に1人の率では少な過ぎる(勲章の価値観はクォリティと希少度にも支配されるが)。因みに私自身は勲3等瑞宝章であった。
終りに、この稿を借りて、木羽敏泰・瀬戸(兄弟)・鈴木進それから川上道夫等々の諸先輩に感謝します。
日本化学会・学術賞を受賞して

東北大・多元研 山内清語 (昭和46年卒)
昨年度(2002年)に,「新しい電子スピン共鳴 (ESR) 法による励起状態研究の新展開」というタイトルで,日本化学会の学術賞を受賞しました.
この機会に少しESRのことを書きたいと思います.ESRの研究はNMRと原理が同じであるのにマニアックな研究と思われがちです.これは電子スピンが周りの環境に対して極めて敏感で変化に富んでいるので,きちんと条件を設定しないと正しい答えが得られないためです.敏感なだけに,条件が合えばこれほど強力な分光法はないのですが,NMRのようにほとんどすべての系には適用できないので,狭い領域で研究をしているような印象も受けます.研究者は物理化学者が多く,時として得意の原理原則の暗闇に入ってしまうこともあり,こういう印象を強めているのかもしれません.ラジカルとかの危なさそうな系が得意の対象ですし,不安定種と言うことで日常的なものから遠いような印象も受けます.しかし反応の中間体に関して言えば,ほとんど常磁性種でESRの研究対象です.生体系や物質系にもたくさん常磁性種があります.我々も,いろいろな系を経験して最大限にESRの能力を引き出していきたいと努力しています.気軽に声をかけて頂ければ,ESRをもっと身近なものに感じていただけると思います.
考えてみれば、私を含めて多くの物理化学者はこれまで,電子スピンをESRなどの分析手段と認識して研究を行なってきました.しかしこれからは,電子スピンを積極的に利用することが重要になるはずです.物理、工学分野では既にスピンによる物性の制御が大きなプロジェクトとして行なわれています.化学でも積極的に電子スピンを使っていく事が必要でしょう.我々も電子スピンによる励起状態や反応中間体寿命の制御の研究を始めました.流行りのEL素子も,今や三重項が重要なポイントです.タンパク質にラジカルを導入して、その周りの状態の解明や2個導入してその間の距離を測定し,タンパクの3次元構造を明らかにする研究も進んでいます.光などでもっと自由にスピンの生成・消滅が制御できれば、スピンによる物性や反応の制御ももっと現実味を帯びてくるでしょう.ESRを若い人にわかってもらう努力も必要です.これに対処するために,今年からESRの夏の学校を始めました.8月に3日間仙台の茂庭荘で行ないますが、どういう結果になるかとても楽しみです.始めたからには、継続は力なりで10年は頑張りたいと思います.10年後はどうなっているでしょう.そう停年の年ですね.
少し話は変わりますが、忙しい時代になりましたね.昔の大学院は本当にのんびりしていました.野添杯のシーズンは、週に3回は野球の練習をしました.中島先生も安積さんも藤村さんも,皆一生懸命でした.昼休みはほとんどバドミントンをしていました.飲みに行く機会もかなり多かったです.学会への出席はスタッフも年に一度でした.私が博士課程を終わるまでに出た学会は2度だけですが、これも普通でした.今なら修士でこの程度は出るでしょう.学会の後は,スタッフも一緒に研究室旅行でした.楽しかったですね.今の先生は,年に5‐6回学会に出席しますが,ほとんどとんぼ返りです.海外の出張も同じようなものですね.これだけのんびりしていても人が育ったのは、ゆっくり考える時間があったためと,上のような遊び以外の時間はほとんど研究に打ち込んでいたためでしょうね.研究には皆,かなりしつこかったのを覚えています.ドイツなどのヨーロッパの大学院生や友人を見ていると昔の日本と変わらないような生活をしています.今のような忙しい生活をしてもゆったりした生活をしてもさほど変わりはないようです.それならゆったりした方が絶対いいです.いろんな経験をして人生を楽しみたいですよね.一度ゆっくり考えてみたいものです.でもなかなかそういう勇気を出せないのが現状です.2年ぐらい成果が出ないとその後どうなるのか怖いですね.賞をもらったご褒美にちょっとやってみましょうか.皆さんどうですか?
日本分析化学会学会賞を受賞して
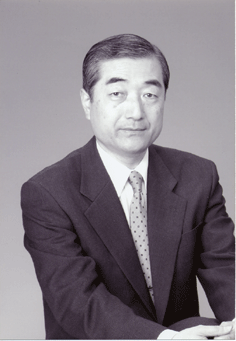
渡會 仁(昭和44年卒)
2003年9月に仙台で開催されました日本分析化学会第52年会において、学会賞を授与されました。本同窓会よりそのことについて寄稿のお誘いをいただき、大変ありがたく思っている次第です。
私は40Sの学年に属しております。当時の教養部での講義は、私にとっては興味深いものが多く、文系の勉強にも随分時間を費やしました。これは、希望する化学科に進学するためばかりではなかったように思います。志望研究室を決める際は、当時は中西香爾先生、齋籐一夫先生、向井利夫先生、中島 威先生、伊東 椒先生等のお部屋を数人で訪ねてお話を伺いました。今ですと、パワーポイントで最新の研究成果の説明を受けるところかと思いますが、当時は教授のお話の端々から研究に対するお考えを探ろうと、皆集中して耳を傾けました。結局、私は小泉正夫先生の理論化学講座を希望し、昭和43年度配属の4年生7人に加えていただきました。修士課程では、國分先生、菊地先生に直接ご指導をいただき、実証により一つの結論を言い切るまでの苦労を学ぶことができました。そして、昭和46年の4月に鈴木信男先生の分析化学講座に教務技官として採用していただき、二相間分配の速度論を研究テーマとして、分離分析化学の分野に足を踏み込むこととなりました。当時の私にとって、ろ過や抽出を繰り返す分析化学操作は、経験と知識を必要とする難解なものに思われました。しかし、鈴木先生は、混沌の中にも法則性を見つけるというデカルトの方法論を分析化学の研究の中で展開しておられるように思いました。
この度の受賞題目は、「液液界面反応と微粒子泳動に関する分析化学的研究」でした。液液界面反応については1981年から82年にかけて、アリゾナ大学のフライザー教授の研究室で行った、溶媒抽出速度における界面の役割の研究が進展したものです。後に高速攪拌法と名付けた界面反応の測定法の開発がブレークスルーとなりました。帰国後、すぐに秋田大学教育学部に転出し、安倍信夫教授の化学第一研究室にお世話になり、学生とともに11年間、液液界面の測定法を工夫しつつ、研究に打ち込みました。界面反応の全内部反射測定も当時の実験の中で工夫されたものでした。秋田大では、新しい液相分離化学を目指してマイクロエマルションやマイクロカプセルを分離媒体に利用し、また、レーザーや交流高電圧によって顕微鏡下の液体を動かす実験も試みておりました。1993年(平成5年)、大阪大学に転任し、分析化学講座を担当することとなりましたので、界面反応、泳動分析、超分子試薬を研究のキーワードにいたしました。まず、界面反応の直接測定法が必要であったため、二相ストップドフロー法や遠心液膜法の開発を進めました。そして、界面錯形成反応における界面の触媒機能を解明し、また、界面吸着錯体の集合反応やその分子認識機能を見出しました。遠心液膜/顕微ラマン法は、界面反応の直接測定法として特に有効な方法となりました。また、液液界面に吸着した単一蛍光性分子の面内拡散速度の測定により、界面ナノ領域の粘性を評価する方法を提案しました。現在は、レーザーの第二高調波発生(SHG)スペクトルによって界面吸着分子のCDスペクトルを測定する方法や、マイクロシースフロー/顕微蛍光法により10μ秒程度の界面反応速度を測定する方法を開発しております。液液界面は、今後、生体分子の機能分析の場として利用されるものと思います。
一方、泳動については、40kbp以上のDNAや分子量10万以上のタンパク質は通常の方法では分離が困難であることから、このような液中微粒子の単一微粒子レベルでの分析を可能とする新しい泳動原理の開拓を進めました。そして、光の分散力と光熱変換効果を利用するレーザー光泳動法、多重極交流電場を利用する誘電泳動法、磁気力を利用する磁気泳動法、及びローレンツ力を利用する電磁泳動法等を開発しました。以前から、分離のポイントは移動を制御することだと思っていましたので、それを微小空間における外場勾配(分離力)により実現しようという発想です。このような概念は、微小領域における種々の外場設計法の進展により、細胞や染色体等の生体微粒子の顕微泳動分析法として発展しつつあります。特に、最も力を入れている超伝導磁石を用いる種々のマイクロ分離分析法の開発は、分析装置に新たな一群を形成するものと期待しています。
分析化学は「自然と計測」をテーマとする間口の広い学際化学ですが、何ができていて、何ができていないかは比較的見定めやすい分野であると思います。いまだ揺籃期の「界面・微粒子の分析化学」ですが、バイオ・素材・環境との関連が極めて深く、しかも未来の分析機器開発の可能性に溢れる魅力ある研究分野の一つです。
今回の受賞は、多くの方々のご指導、ご協力によるものであります。この場をお借りして心よりお礼を申し上げますとともに、本同窓会の皆様の益々のご発展を祈念いたします。
2003年6月
日本化学会進歩賞を受賞して
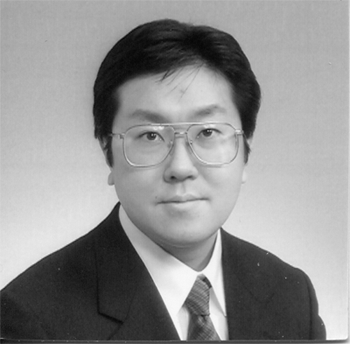
松尾 司(平成6年卒)
このたび、日本化学会から「ケイ素基の特性を活用した四員環及び五員環を機軸とするπ電子系アニオン種に関する研究」という業績で、平成14年度進歩賞をいただきました。受賞を報告するにあたり、学部学生の頃から熱意ある御教授と温かい励ましを賜りました櫻井英樹先生(東北大名誉教授)、実際に業績の大部分を御指導して頂きました関口 章先生(筑波大教授)に心より深く感謝申し上げます。
受賞の対象となりました「ケイ素置換π電子系」の化学は、櫻井研究室の大きな研究テーマの1つでした。中平先生(電通大名誉教授)、飛田先生(無機化学教授)のケイ素置換エチレンに始まり、ケイ素置換アセチレン類の反応では細見先生(筑波大教授)、坂本先生(有機第二助教授)、ケイ素置換ベンゼンでは江幡先生(NTT基礎研)と、櫻井研の多くのスタッフの先生方、先輩方がこの研究に取り組んでこられました。関口先生がアニオン種の構造研究を始められ、私が4年生の頃は江幡先生が三重項ベンゼンジアニオンの研究を現在助手の瀬高氏とともに展開していました。このような流れの中で私も研究に携わる機会を与えられました(有機ケイ素材料化学実験施設という化学棟から離れた建物で実験していました)。櫻井先生御退官の後も、吉良満夫先生(有機第二教授)はじめ、諸先生方には大変御世話になりました。ここに厚く御礼申し上げます。修士号を取得後、関口先生とともに私は筑波大学に移りましたが、関口研究室の立ち上げをしながら一緒に研究してくれた筑波大学の学生の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。また、研究を進める上で筑波大学の先生方には大変御世話になりました。心より感謝申し上げます。
今回の主な業績は、シクロブタジエンジアニオンの芳香族性の解明です。四員環6π電子系シクロブタジエンジアニオンは、ヒュッケル則から芳香族化合物と予想されますが、合成例はなく性質は未知でした。合成が困難な理由としては、2つの負電荷間の静電的反発が大きいこと、四員環の環歪みの問題、そして、アニオン種が空気や水に対して不安定である合成技術上の問題が挙げられます。私はケイ素置換シクロブタジエンを配位子とするコバルト錯体と金属リチウムとの反応によりシクロブタジエンジアニオンをジリチウム錯体として合成しました。X線結晶構造解析からシクロブタジエンジアニオンの四員環が平面正方形構造であることを解明し、NMR研究から6π電子系反磁性環電流の存在を明らかにしました。小林長夫先生(機能分子教授)、石井先生(同助手)には、シクロブタジエンジアニオンの磁気円二色性スペクトル(MCDスペクトル)を測定していただき、二重に縮退したHOMOと1つのLUMOを合わせ持つ分子であることが明らかとなりました。
東北大学には構造有機化学、非ベンゼン系芳香族化合物の伝統と歴史があります(まだ正七角形柱碑を拝んでいないのですが)。微力ながら同窓の一人としてシクロブタジエンジアニオンの研究に貢献できたことを光栄に思います。また、シクロブタジエンジアニオンの二電子酸化反応により中性の4π電子系シクロブタジエンに変換しました。これはシクロブタジエンの新規合成法です。さらに、光反応により最小のかご型化合物であるテトラヘドランに変換しました。これらはヘテロ原子が4つ置換した初めてのシクロブタジエンとテトラヘドランです。シクロブタジエンは1970年代には化学における「モナリザ」と呼ばれた化合物であり、同窓の大先輩である正宗 悟先生(MIT教授)が研究されております。
2年程前に私は分子科学研究所に異動となり、川口博之先生(錯体助教授)のグループで新たに遷移金属錯体の合成や反応に関する研究を行っています。金属錯体にとって典型元素の化学は配位子の化学であり、遷移金属の優れた反応性や機能性を引き出す上で大変重要です。現在、配位子から手作りする錯体化学について取り組んでおり、徐々にではありますが研究の幅を広げていきたいと考えています。若いうちに環境を変えていろいろな研究者と出会い、いろいろな化学を経験できることを幸せに思います(苦労も同じくらい感じますが)。また、この賞を受けることができたのは、分子研に異動して日が浅いにも関わらず東海支部から推薦していただけたからであり、茅 幸二先生(分子研所長)、田中晃二先生(錯体教授)、藤井正明先生(東工大教授)をはじめとする分子研の諸先生方に厚く御礼申し上げます。
最後に、これからも仙台で学んだことを忘れずに研究に鋭意専心していきたいと思います。東北化学同窓会の皆様のご健康とますますの御発展をお祈りするとともに、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
日本分析化学会奨励賞を受賞して
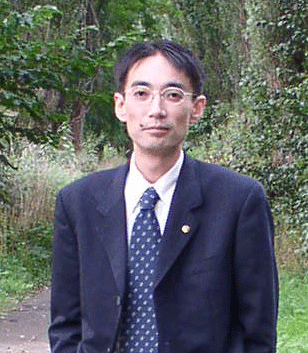
西沢精一(特別会員)
このたび,日本分析化学会より平成14年度奨励賞をいただく栄誉に恵まれました。受賞の報告にあたり,終始暖かく御指導いただきました分析化学研究室・寺前紀夫先生に深く感謝申し上げます。そしてこのような賞をいただくことができましたのも,早下隆士先生,内田達也先生(現東京薬科大学生命科学部),山口央先生の御指導と御協力をいただいたこと,さらには優秀で愛すべき学生の方々に恵まれたことによるものであり,皆様に深く感謝申し上げます。
今回の受賞対象となった研究課題は,「分子複合体形成に基づく分析試薬の開発と液液界面イオン認識」というもので,特に水素結合形成を駆動力とする有機分析試薬開発において,いくつか面白い成果を出すことができました。それらは,私一人の力では全く不可能なことであり,まさに分析化学研究室の皆様と化学教室の皆様の御支援の賜物であると強く感じております。
私は,博士課程(東京大学大学院理学系研究科化学専攻・梅澤喜夫研究室)修了後,平成8年4月より,寺前研究室の助手として勤務させていただいております。早いもので,もう丸7年余になります。この間,平成12年3月には,日本化学会進歩賞をいただく栄誉にも恵まれました。思い出してみますと,寺前先生には,「もう一度学位を取るつもりでがんばること,自分に厳しく,学生に感謝,そして和合」と御指導をいただき,東北大学での生活がスタートしました。元来,生意気であり,また世間知らずの私が,こうしてなんとかやってこれましたのも,ひとえに寺前先生のおかげと心から感謝しております。また,私の未熟な指導に耐え,そして研究を展開してくれた学生の方々には,ただただ感謝の一言です。年寄りじみているかも知れませんが,研究生活を共に過ごした学生の皆さんが大きく成長していく姿は頼もしく,とても嬉しく思います。
いま,こうして恵まれた環境のなかで,教育と研究に携わさせていただけることに深く感謝するとともに,その責任の大きさを痛感しています。初心を忘れることなく,自分の教育,研究姿勢を常に省みながら,日々精進していく覚悟です。今後とも同窓会の皆様のなお一層の御指導と御鞭撻を賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。
有機微量分析懇談会標準試料検定特別功労賞の受賞にあたって

元素分析室 安東比那子
目本分析化学会有機微量分析研究懇談会の創立50周年記念大会シンポジュウムが5月8日(木)〜10日(土)、かずさアカデミアホールで開催され、当元素分析室が標準試料の検定に貢献したということで表彰されました。
標準試料の検定とは元素分析の測定には検出感度を求めますが、その時に使用する標準試料は100%に近い精度が要求されます。よく使われるものにはAntipyrine, Acetani1ideがありAntipyrineはC=70.19%、H=6.43%、N=14.88%, AcetanilideはC=71.09%、H=6.71%、N=10.36%の組成であり、含有元素の種類や含有率が多数の有機化合物の平均的な姿を代表しているからだと思います。それと精製がしやすく純品が得られること、空気中に安定で揮発性、吸湿性が無いなどの理由も挙げられます。
こういった標準物質で分析装置の検出感度を求めると、これに近い組成や性格のサンプルでは正しい分析結果を得る事ができますが、かけ離れた組成や性格のものでは次第に期待した分析緕果が得がたくなります。例えばC,Hにたいして以上に多いNが含有している
サンプルにはThiourea C=15.78%, H=5.30%, N=36.80% を使用するか、又はAntipyrine, Acetani1ideでの検出感度でThioureaの測定値が±0.3%に入るかどうか測定してみます。
そのために標準試料はC,Hだけのものから、ハロゲン、硫黄の入ったもの、あるいは種々の金属の含まれているもの、揮発性、揮散性のものなどキシダ化学から元素分析用の標準試料として50種類以上出されています。合成された標準試料は、一つの標準試料につき数ヶ所の測定室に依頼して測定値をだしてもらい、その標準試料が使用できるかどうかを検討委員会で検討されてきました。当測定室がその測定依頼を引き受けていたことに対する受賞です。
元素分析が今日あるのは、これら地道な努力をしてきた人達に依る所が大きいと思います。当測定室も野村先生が大正10年代に外国留学中に元素分析の本に最初に載っている微量分析の元祖と言われているPreg1から測定方法を教わって来て始めたと聞いております。それ以来当元素分析室は微量分析装置の進歩と共に歩んできました。亦多くの人達がこの測定室を支えてきました。今度の受賞をその人達も喜んでおられると思います。
副賞としていただいたクリスタルにはPreg1の測定装置が彫られておりとても素敵なものです。長い間支えていただいた化学教室のみなさまに感謝しますと同時にこれからも当元素分析室を宜しくお願いいたします。
日本化学会BCSJ賞を受賞して
筒井 忍(平成4年卒)

このたび、日本化学会よりBCSJ賞を頂きました。櫻井英樹先生、坂本健吉先生、江幡啓介先生、甲千寿子先生との共同受賞です。BCSJ賞は、日本化学会欧文誌(Bulletin of the Chemical Society of Japan)の月間最優秀論文の著者全員に授与されます。受賞論文の題名和訳は「2,3,5,6-テトラシリルキノン-1,4-ベンゾキノン類および関連化合物の合成、構造および光反応」です。今回の業績は、東北大学櫻井研において行った研究成果を基に、最終的に理化学研究所フォトダイナミクス研究センター坂本チーム(坂本先生が東北大学と兼任でチームリーダーを務めている)で完成させたものです。受賞の報告に際し、共著者の先生方をはじめとする同窓会の諸先生、先輩方に深く感謝致します。
BCSJ賞の特典としては、1)欧文誌の表紙を飾ること、2)日本化学会春季年会において受賞講演を行うこと、3)共著者一人ずつに賞状が授与されること、などが挙げられます。1)に関しては2002年12月号に掲載されました。2)3)に関しては2003年3月の春季年会において受賞講演および賞状授与がありました。共著の先生方のご配慮により、私が代表して受賞講演を行いました。
受賞論文の概略を記します。π電子系化合物に対して多数のシリル基を導入すると、母体化合物には見られない特異な構造および性質が発現することはよく知られています。今回我々は、最も基本的なπ電子系化合物の一つであるp−ベンゾキノン(以下キノン)に注目し、そのテトラシリル置換体の合成を検討しました。その結果、テトラハロゲン置換キノンとクロロシラン類から誘導される1,4-ビスシロキシ-2,3,5,6-テトラシリルベンゼン類をクロロクロム酸ピリジニウムで酸化することにより、目的とするテトラシリルキノン類の合成に成功しました。この合成法を応用することにより、キノン環の任意の位置に、任意の数のシリル基を導入することも可能となりました。また、テトラシリルキノン類の構造は、シリル基のかさ高さに大きく依存することも明らかにしました。特にテトラキス(トリメチルシリル)キノンは、キノン環がひずんだいす型配座を取るとともに、光照射によりシリル基の転位を伴う特異的な分子内転位反応を起こしました。このように、多数のシリル基が置換したキノンは、母体化合物には見られない特異な物性および反応性を示すことを明らかにしました。
欧文誌について振り返ってみると、私がまだ櫻井研の学生だった頃、櫻井先生は欧文誌の編集長としてその活性化にご尽力されていました。活性化の流れに沿った形で、表紙の刷新、内容の大幅改訂、BCSJ賞の新設、電子ジャーナルとしての公開などが相次いで行われ、欧文誌が質・量ともに格段に向上してきたのは周知の通りです。そのような経緯を持つ欧文誌において、櫻井先生とともにBCSJ賞を受賞出来たことは私にとって大変嬉しい出来事でした(櫻井研卒業生の受賞はあるものの、櫻井先生御自身の受賞は初めてだと思います)。一人の日本人化学者として、欧文誌のさらなる発展を願う次第です。
最後に近況を述べますと、私は現在、理化学研究所フォトダイナミクス研究センターで研究生活を送っています。当センターは仙台の青葉台に位置しており、自然環境に恵まれているという長所と、蔵書や福利厚生設備が不十分であるという短所を併せ持っています。そのため、今でも東北大理薬キャンパスの図書館や生協には大変お世話になっています。大学を訪れる度に、自分がいかに恵まれた環境で学生生活・研究生活を送ることが出来たかを実感しております。
末筆ながら、東北大学理学部化学科の益々の発展を願うとともに、今後とも同窓会の皆様のなお一層のご指導と御鞭撻を宜しくお願い申し上げます。