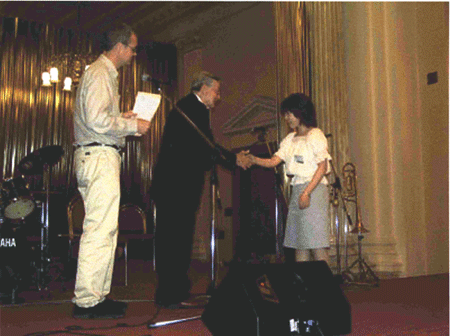
The Nitric Oxide Society Young Investigator Award 受賞に当たって
理学研究科 化学専攻 佐藤 裕子
第2回国際NO学会はプラハで開催された。チェコの首都であり、ヨーロッパの魔法の都、北のローマ、ヨーロッパの音楽学院と称されたかつてのボヘミア王朝の中心地である。数年前その歴史的な魅力に惹かれて一度訪れたことがあった。私は国際学会へ参加し最新の研究に触れられる期待の他に、あの美しく活気に満ちた国を再度訪れることができるという喜びを感じていた。
一酸化窒素(NO)の生体内における重要性が確認されてからNOに関する研究が盛んに行われ、毎年膨大な数の論文が発表されている。1998年にはNOの生理学的な重要性を発見した研究者がノーベル賞を受賞した。NO学会は化学や生物、医学、工学といった様々な観点から行われているNOについての研究結果を交換し合い、さらなるNOの可能性を追求する場である。私が所属する清水研究室では数年に渡ってNO合成酵素に関する研究を行ってきた。NO合成酵素とはその名の通り、生体内でNO合成反応を触媒する酵素である。今回の発表のテーマもそれに沿ったものだった。ポスターではあったが英語での説明には不安があったため、前もって原稿を作成し説明練習を何度か行っていた。しかし、本番になるとそんなものはすっかり吹き飛んでしまい、勢いだけでしゃべりまくっていたような気がする。とにかく1時間のセッションがとても短く感じた。頭の片隅で、同行していた清水教授から、私自身をYoung Investigator Awardにノミネートした旨を聞いたような気がしたが、そんなことは最後のGALA Dinnerまですっかり忘れていた。もちろん自分が受賞することなど想像すらしなかった。
GALA Dinnerはヨーロッパの文化の歴史を感じさせる美しいホールで行われた。豪華な装飾や華やかな音楽に圧倒されるようなパーティーだった。そうこうしているうちに私の名前が呼ばれた。受賞したことを自覚するのにしばらくの時間が必要だった。階段を使わずにステージに上がろうとしたり、プレゼンターであるノーベル賞受賞者のFurchgott氏の手を長いこと握りしめていたことを考えるとひどく動揺していたように思う。その後の祝福の握手攻めの間も気分は高揚したままだった。ホテルに帰っても寝付けず、チェコ産のバドワイザーを一本空けてからベットに入った。(余談ではあるが、チェコは黒ビールと同じくらいバドワイザーが美味で、有名である。現地の人々はアメリカ産は偽物だとすら言う。)
この賞は言うまでもなく今までこの研究に携わってきた諸先輩方、及び数年に渡ってご指導頂いた清水教授及びに佐上講師の功績によるものである。その点で私はこの賞を誇りにし、同時に感謝の念をここに表する。
プラハという町が私に幾つもの贈り物をくれたような気がしてならない。ドボルザーク・ホールやオペラ座で聞いた美しい音楽、町のいたるところにある歴史深い建物、喉を潤してくれた黒ビール等々、私は様々にプラハの滞在を楽しんだ。我々が帰国後、プラハで大洪水がおこったが、私は旅先で世話になった人々や、美しい町並みを思い、居たたまれない気分になった。その後、無事復興しつつあることを聞き、安堵している。機会があればこのすばらしい経験をくれたあの町を再度訪れてみたいと考えている。
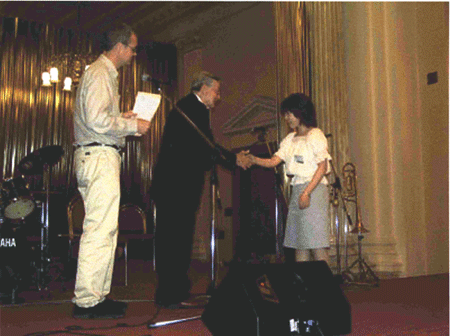
写真の説明:ノーベル賞受賞者であるFurchgott教授より賞状を手渡された。
日本化学会学生講演賞を受賞して
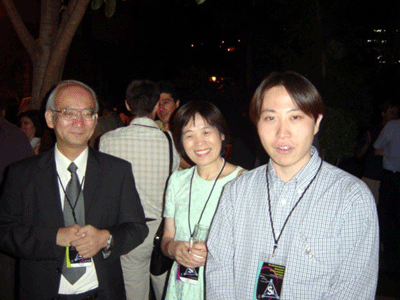
石田真太郎(平成14年度卒)
平成15年3月に開催された日本化学会第83春期年会における講演「初めての安定なトリシラアレン」に対し学生講演賞を受賞しました。学生講演賞は本年度から始まった新しい賞で、学生のB講演(発表15分、質問5分)に対して贈られるものです。共同研究者の吉良満夫教授、岩本武明博士をはじめとする吉良研究室の皆様に厚く御礼申し上げます。
講演賞の賞状を見ると、研究室での思い出がいろいろと湧いてきます。私が三年後期に吉良研究室に所属した当初は、まだ珍しかったインターネットに触ってみたり、マッキントッシュでアイコンを作る事に凝ってみたりなど、どう考えても真面目な学生ではありませんでした。態度も大きかったと思います。そんな私に研究の面白さを示してくださった諸先輩方には本当に感謝しています。
演題に関する研究は私が博士課程に立案したテーマで、上手く行くかどうかの具体的な見通しは全くありませんでした。ただ漠然と出来るんじゃないかなあとだけ考えていました。当然最初は苦労していたのですが、その時に「実験をしている人の勘、感覚は当たるものだから、もうちょっと粘ってごらん」と励まされた事は強く記憶に残っています。
悩み事があるとよく最近建てられた総合棟の屋上に行っていました。そこからの眺めはおそらく仙台一で、太平洋も蔵王連峰もよく見えました。ぼんやり眺めていると段々とポジティブになれるから不思議です。
研究に取り組んでいた博士課程時代は、臭い言い方をすれば青春とも呼べるような熱さがあったと思います。昼に夜にああでもない、こうでもないと研究について、あるいはもっとくだらない事を語り合ったり、飲み会で文字通り打ちあがったりしたことなどがいくつも思い出されます。そういった出来事の一つ一つが見えないところで自分の糧になっている様な気がします。学部時代を含めて幸せな学生生活を送る事が出来ました。
東北大学の研究環境がこの良い学生生活を後押ししてくれたのだと思います。日常では忘れてしまいがちですが、この素晴らしい研究環境は化学教室の諸先輩方が培って来たもので、その伝統が活きているのは素晴らしい事だと実感するようになりました。これまで自分が教わった事、受け取った事をなるべく後輩にも還元するようにしたつもりですが、十分に出来なかった部分もあり、そこが若干心残りです。
学生講演賞は本年度から始まった賞とのことで、この賞の価値を決めるのは我々受賞者のこれからであると考えられます。そのためプレッシャーを感じますが、本賞の価値を高められるように努力していきたいと思っています。
第52回錯体化学討論会ポスター賞を受賞して

松田 明恭
私は平成14年9月30日から10月2日まで東京大学駒場キャンパスで行われた第52回錯体化学討論会においてポスター賞を受賞いたしました。今回の発表のタイトルは、「塩基の配位していないシリル(シリレン)鉄錯体の合成および構造」であり、鉄-ケイ素二重結合と鉄-ケイ素単結合を同時に持つシリレン(シリレン)錯体の合成と構造解析についての発表を行いました。
シリレン錯体、特にシリル基とシリレン配位子を同時に持つシリル(シリレン)錯体は、ケイ素-ケイ素結合の生成や切断を伴う様々な触媒反応の重要な中間体と考えられていますが、シリレン錯体は一般的に不安定でこれまで合成例はほとんどありませんでした。そこで、我々無機化学研究室では、シリレン配位子上にかさ高い置換基を導入することでシリレン錯体の単離を目指してきました。私は、シリレン配位子上にかさ高いメシチル基を二つ導入して、鉄錯体としては初めての塩基の配位していないシリル(シリレン)錯体の合成と構造解析に成功しました。その結果、この錯体はこれまで知られている錯体の中で最も短い鉄-ケイ素結合距離を持つことなどから、鉄-ケイ素間の結合が二重結合であることが明らかになりました。シリル(シリレン)錯体上では、ケイ素上の置換基がシリル基からシリレン配位子へ転位する1.3-転位や、シリル基が鉄からシリレン配位子上に転位する1,2-転位を起こす可能性があり、これらの転位反応は、金属触媒によるケイ素化合物の変換反応のキーステップであると考えられ、非常に興味が持たれます。今回合成した錯体は、非常に安定であるため、反応性を研究するのに適しており、現在はそのような転位反応の観測を目指して研究を行っています。
今回の錯体化学討論会は私にとって初めての学会発表でしたので大変緊張しました。当日は発表時間の1時間半の間ほぼ休み無く、たくさんの方々に発表を聞いていただきました。多くの方から有益な助言を得ることができ、大変貴重な経験をすることができました。
最後になりましたが、今回のポスター賞は、私が研究室に配属になってから大変お世話になりました無機化学研究室の荻野博教授(現放送大学教授、東北大学名誉教授)、飛田博実教授、上野圭司博士(現群馬大学助教授)、橋本久子講師など教官の方々や、諸先輩方のおかげで受賞できたと思っております。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。
東北大学総長賞を受賞して
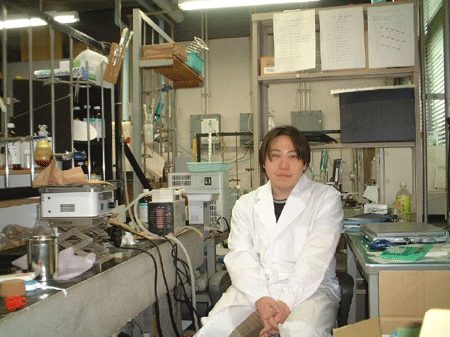
石田真太郎(平成14年度卒)
私の博士論文「初めての安定なジアルキルシリレンおよびトリシラアレンの合成、構造および反応」が平成14年度東北大学総長賞の対象となり、平成15年3月の博士号授与式において表彰されました。東北大学総長賞は各学部の優れた博士論文に対して贈られるとのことで、このような評価を受けたことを非常に光栄に思っています。博士論文を指導してくださった吉良満夫教授、助手の岩本武明博士をはじめとするお世話になった方々に深く感謝いたします。
シリレン(R2Si:)とはカルベンのケイ素類縁体の事で、ケイ素化合物の重要な反応性中間体のひとつです。シリレンの電子状態や反応性は置換基によって大きな影響を受けることが知られており、特に置換基Rが特殊なアミノ基やη5-ペンタメチルシクロペンタジエニル基のシリレンは電子的に強く安定化され単離する事が出来るようになります。一方、アルキル基を用いた2配位ジアルキルシリレンは反応性が極めて高く、単離してフラスコの中に取っておけるような化合物ではありませんでした。
我々はアルキル基を工夫し速度論的安定化を行うことによるジアルキルシリレンの単離を検討しました。試行錯誤の末単離に成功したジアルキルシリレンはそのエックス線結晶構造解析やスペクトルから置換基による電子的安定化はこれまでの安定シリレンに較べ著しく小さいことがわかりました。実際このジアルキルシリレンは反応性が高く多重結合や極性のある結合と容易に反応します。
博士課程でこれからのテーマを考えていたときに、シリレン骨格をケイ素でつないだトリシラアレンR2Si=Si=SiR2の合成がチャレンジする価値があるのではないかと思いつきました。なぜならsp混成のケイ素を持つと考えられるケイ素の集積二重結合や三重結合化合物は報告例が無く、どのような性質を示すのかは全く予想が付かないからです。
高周期14族元素の多重結合は構造や性質が炭素のものとは異なる場合が多く、容易に多量化する傾向があるので、置換基にはシリレンと同じアルキル基を選択しました。これは2価ケイ素化合物が単離できるならケイ素の二重結合も単離できるだろうと言う単純なアイディアと、出発原料として反応性の高いジアルキルシリレンを用いることが出来るので容易にトリシラアレンの前駆体を合成出来るという利点があったためです。
合成ルートは種々検討しましたが、最終的にトリシラアレンを暗緑色結晶として単離する事に成功しました。エックス線結晶構造解析によるとトリシラアレンのSi=Si=Si部分は折れ曲がっており、低温、結晶中でさえも中心ケイ素は末端ケイ素を軸に縄跳びのように回転していることが解りました。この理由は理論計算から明らかになり、トリシラアレンは炭素と異なり折れ曲がった構造が最安定であること、角度の変化に対して柔軟であることが解りました。これは炭素のアレンとは全く異なった特徴です。
ジアルキルシリレンおよびトリシラアレンの合成を通じて、従来の炭素中心の有機化学の構造・反応論を問い直し、14族高周期元素を包括する新しい化学的物質観の構築に貢献するという吉良研究室の研究目標に微力ながら参加することが出来ました。東北大学化学教室にある自由に研究を行う伝統が、私の研究の後押しをしてくれたのだと思います。
平成14年度東北大学総長賞を受賞して
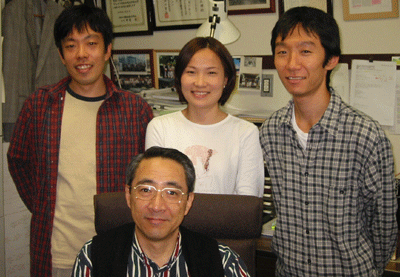
佐藤 隆章
学部生の卒業発表も終わり、修士課程が始まろうとしていた頃、教授室のドアをノックしている自分がいました。今までまともに教授室に入った事も無く、かなり緊張しましたが、今後の研究の事で平間正博教授に聞いていただきたい事があり、小さな勇気を出してドアをたたきました。今だ大学受験生の頃の受身的な勉強スタイルから抜けられないまま研究室配属された当時、先輩方が研究過程でぶつかった問題に、自らアイデアを考え、取り組んでいる姿が衝撃的だった事を覚えています。学問の研究というのは、今までの勉強と異なり、新しい考えや問題点に対する解決策を通して自分を表現していく場所なのだと思いました。すると俄然やる気が出て、この先輩方に追いつき追い越そうと研究に励みました。ところが、そう簡単に自分が思ったようには行かず、何も結果が出ないまま学部生活は終わりをつげました。
学部時代の研究がまったくうまくいかず、修士課程の開始にあたり新しい研究テーマに変わる事になりました。我が研究室では、有機合成を用いた天然物の全合成が主題であり、海産生食中毒原因物質シガトキシンと抗腫瘍性抗生物質エンジイン類の全合成が2大テーマでした。僕も御多分もれず、シガトキシンの全合成研究に携わる事になりました。しかし、僕の中で常に頭の中をグルグル回っていた事は、自分の力で科学に取り組めるようになりたい、科学を通して自分を表現できるようになりたいということでした。今思えば、単なる我がままな思い込みでしたが、当時は、大人数で取り組むシガトキシンより、1人で取り組むような小さなテーマの方が良いと思っていました。なまぐさな僕は、自分を追い込むような環境でないと本気で考えない。研究がうまくいかない時に、誰にも言い訳ができないような自分1人の環境でなくてはだめだ。また、研究の立ち上げから完結まで携わり、1つの作品を完成させたいと考えていました。そして、小さな心臓をバクバクさせて、教授室のドアをノックしました。
研究テーマを変えて頂けませんかと平間先生に相談すると先生は親身に僕の話を聞いて下さりました。嫌々研究するより学生のモチベーションが高い方が良いと言う事で新しくメリラクトンAという天然物の合成研究に携わる事になりました。今思えば、研究室という集団の中で、一個人があれしたい、これしたいと勝手なことを言っていたら、研究室が回らないだろうと思いますが、その上で親身に僕の話を受け止めてくれた平間先生に感銘を受けていました。新しい研究テーマが開始されると同時に新たな問題が発覚しました。それは、直接指導して下さった井上将行助手(現講師)が、頭が良すぎるということでした。自分の力で科学に取り組めるようになりたいと新しいテーマに変わったのに、井上先生の下では次々に問題が解決されていきました。話を聞いてそれに従っていれば、勝手に研究が進展していくのです。これは、本当にあせりました。自分の考えを表現するどころではない、受身もいいところでした。そこで、問題点にぶつかったら、まず自分で調べ、そして自分のアイデアを持ってから相談するというスタイルにする事にしました。慣れないため時間がかかり、持っていったアイデアも次々に蹴散らされるという状況でしたが、それをひたすら続けました。そんな僕の姿勢を理解してくれたのか、井上先生も有機化学の基本から科学者としての姿勢まで、さまざまな事を教えて下さいました。そのかいあって、修士過程2年の頃には、少しずつ有機合成化学というものがわかってきて、研究が楽しくなってきました。井上先生に持ち込むアイデアも、10回に1回くらいは「悪くない」(かなりの誉め言葉らしい)と言われるようになりました。
そして、研究目的であるメリラクトンAの全合成を達成する事ができました。この研究に一区切りついて考え直した時、自分を表現できたのかと思うと、答えはノーだなと思います。表現したというより、すごくたくさんのことを学ばせて頂いたという感じです。そんなすばらしい機会を与えてくださった平間先生、井上先生に深く感謝いたします。
小林正治
この度、青葉理学振興会賞を受賞いたしました。青葉理学振興会賞は、理学研究科および生命科学研究科の大学院生を対象としたもので、研究業績や学術論文を基に審査されます。女子学生を対象とした「黒田チカ賞」とともに、大学院生の目標となる賞です。恩師である平間正博先生から推薦のお話をいただいたとき、「まさか私なんかが・・・」と、とまどいと信じられない気持ちでした。しかし、それと同時に、私のような未熟者を推薦してくれたことに、この上ない喜びと感激を受けたのをはっきりと覚えています。そして、まさか本当に受賞することになろうとは・・・。
私は、平間研究室で修士課程を修了した後、2年間、民間会社に勤務し、博士課程に編入学しました。大学に戻ることを決意した理由はいくつかあるのですが、その中の一つに、修士課程で完結できなかった仕事を、是非、自分の手で完結させたい、という強い思いがありました。結局、その熱意が実りとなり、幸運にも博士課程の1年目に目的を達成することができました。やり遂げたときの充実感と達成感は今も忘れられません。
しかし、実はそのとき以上に喜び、化学の世界にのめり込むきっかけとなった出来事があります。それは、私がまだ修士課程1年生だったときの話。私も皆さんがそうであった(ある)ように、悩める一人の学生でした。大人しく、平間先生にはさほど印象に残らない学生であったと思います。有機化学に嫌気がさし、逃げたい気持ちで就職を決意したのもこの頃です。当時、私はある1つの反応が全くうまくいかず、苦悩の毎日でした。同部屋には教官がおらず、ある程度独立して(見捨てられて!?)実験していた私は、とにかく自分自身で解決するしか道はありませんでした。自立心が強いせいか、人に聞くこともあまり得意ではありませんでした。しかし、所詮は平凡なM1の頭脳。大したアイデアや実験技術もなく、泥沼にはまっていきました。そしてそのまま1年が経過・・・。忘れもしないM1の2月1日。ついにその反応がうまくいったのです!間違いなく、今までの生涯で最高の感動でした。家に帰ってから、あまりのうれしさに体が震えだし、その震えが止まらなくなったのを覚えています(結局、夜道を散歩して、どうにか体の震えを抑えましたが)。もちろん、「おまえの苦労なんかたいしたことないよ」と思う方は大勢いるでしょう。おっしゃる通りです。ただ、未熟者には未熟者なりの喜びがあって、こんな些細な経験でも自分自身に自信とやる気がでたのは紛れもない事実なのです。
少々話がずれてしまいましたので、振興会賞のことに話を戻します。博士課程の3年間は、実に充実したものでした。特に、時間の使い方に関しては、2年間の会社経験が生かされたような気がします。大部分の学生の皆さんは、「学ぶため」そして「様々な経験を得るため」に大学に通っていることでしょう。当然です。しかし、私は「学ぶため」という意識はほとんどなく、「仕事する」という意識で毎日通学(通勤?)していたように思います。勤務時間はとにかく集中して自分の仕事に打ち込むこと。そして短期的な目標と期限を設けて、それに間に合うように仕事を進めること。この2つを守りながらやってきたつもりです。もちろん、人それぞれ目標が違いますし、いろいろなやり方があるでしょうが、今、こうして振興会賞を受賞できたことを考えると、私の3年間のやり方も間違っていなかったのではないかとホッとしています。
最後になりますが、熱中できるチャレンジングなテーマを与えてくださった平間先生には心より感謝いたします。また、研究を支えてくれた教官の方々、先輩、学生の皆さん、友人、そして、この受賞を誰よりも喜んでくれた家族に深く感謝いたします。