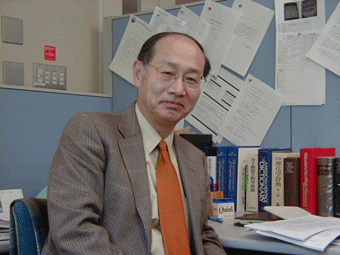
化学教室を終へて
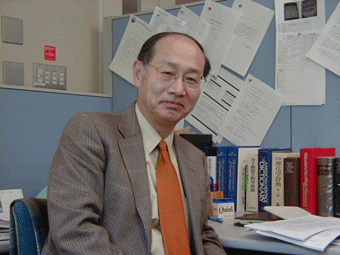
藤井 義明
私が化学教室を一昨年3月に定年退官して,早くも一年半が経とうとしています.この文章は本来ならば昨年の本誌に掲載予定だったのですが,原稿の締切りの12月が,私共の主催した日本分子生物学会とぶつかってしまったことと,私の怠慢のために遅れましたことを先ずお詫びしなければなりません.幸いに分子生物学会は,9,000名を越える参加者を得て成功裏に会を終えることが出来ました.
その後,化学教室はCOEに選ばれて益々発展されている様子で大変喜ばしいことです.
私は,1987年9月から2002年3月まで14年半の間化学教室でお世話になりましたが,多くの優れた先輩の先生方,同輩,後輩の方々,学生にめぐり会うことができて,大変幸せであったと思います.過ぎてしまえばあっという間のような気もしますが,考えてみると種々と貴重な経験をさせていただいた14年半でもありました.
長い間勤めた(財)癌研究所から東北大学化学教室に移るに際して,これからどのように研究を展開させて行くべきかを考えて,遺伝生化学的方法を取り入れた発生の研究なども考えましたが,これは人のことを考えて困難であることが分かり,断念しました.そして暗中模索の中から,むしろそれまでに続けて来たシトクロムP450の異物代謝の研究,ステロイドホルモンの合成に関与するP450の遺伝病のメカニズムの研究,異物代謝P450の外来異物による誘導的発現のメカニズムの研究に焦点をしぼって研究することにしました.幸いにして研究費はがん特別研究と遺伝子発現調節機構の重点領域研究と後に特定領域研究の支援を得て,研究室の立ち上げを行うことができました.この時に癌研から私と一緒に化学教室に移った学振特別研究員井上英史,横谷昇,助教授十川和博君の協力に負うところ大であったと思います.
P450の研究は現在では2000種以上の分子種のP450が報告されていますが,その初期の研究において先端を走ることができたこと,頻度の高い遺伝病として知られている先天性副腎過形成症の主な原因であるP450C21欠損症の頻度の高い原因を見つけることができたのは,研究生や大学院の学生諸君の努力の賜物でした.また,異物代謝P450の遺伝子発現誘導の研究は誘導的転写因子アリルハイドロカーボン受容体(AhR, あるいはダイオキシン受容体DRとも呼ばれる)cDNAの世界に先駆けたクローニングの成功につながり,“内分泌かく乱物質”のCREST研究に採択されて,後半の研究を進める上で大きな推進力を与えてくれました.この研究はその後,低酸素を感知して働く転写因子HIF-1αやHLF, 日周性を統御する転写調節因子ClockやBmal1などが同じ構造モチーフをもつことが解明されて,広く生物の環境応答に働く転写調節因子の遺伝子ファミリーとして働いていることが明らかになっています.AhRの研究も外来異物のセンサーとして働くのみでなく,生殖周期や免疫細胞の分化などにも働いている転写調節因子としての機能が分かって来て,現在も私共に尽きない興味を与えてくれています.
さて,私が化学教室に赴任して数年が経った時に考えさせられたことは,当時13講座あった研究室の中で生物化学に関連する研究室が唯一つであったことです.関連する講座が他にないと言うことは,学生の教育から考えても研究を進展させて行く上でも環境としては良くないことが分かって来ました.互いに関連した領域の研究室間で議論したり,共同研究をしたりして切磋琢磨する機会が必要であることを痛感しました.そこで,生物教室の竹内拓司先生や化学教室の桜井英樹先生と相談して生物教室と化学教室で基礎生命科学専攻を理学研究科の中に作る計画を立て,概算要求の準備が進行をしていた時に,急に理学研究科の大学院重点化構想が具体化して,基礎生命科学専攻の計画は棚上げになり中断せざるを得なくなりました.その後,全学的に生命科学に関する研究をしている研究室を統合して,独立研究科を作る動きが2回おきていますが,私にとりましては,三度目の正直で生命科学研究科の設立が承認されました.この時は,化学教室の荻野博教授が中心になって全学的に話がまとめられました.また,化学教室の方々の理解と協力に感謝しております.しかし,設立された時はもう私の定年退官まで一年を残すのみで私自身にとりましては,あまり益することはなかったのですが,竹内教授と行動を起してから約10年のことで,いろいろな意味で感慨深いものがありました.組織がうまく動いて業績が出るか否かは組織の柔軟な運営は重要な要素でありますが,それよりも重要なことは“人”であることを銘記して,これから生命科学研究科が発展することを祈っています.化学に基礎をおいて生命現象を解くことの重要さは今さら言うまでもないことですが,極最近の例で言えば,昨年線虫の細胞死の研究でノーベル医学生理学賞を与えられた英国のJohn Sulston博士は有機化学者として研究生活をスタートさせています.化学教室の学生諸君の中から切磋琢磨の研究環境の中で多くの若い研究者が育つことを願うものです.
2005年からの国立大学の独立法人化に向けて,化学教室も現在大きな変動期にあると思いますが,この機会を上手くとらえて,さらに飛躍することを祈っております.私も幸いにCRESTの発展継続研究が認められて,しばらくは現在の研究が続けられそうです.
2003年8月
つくばにて
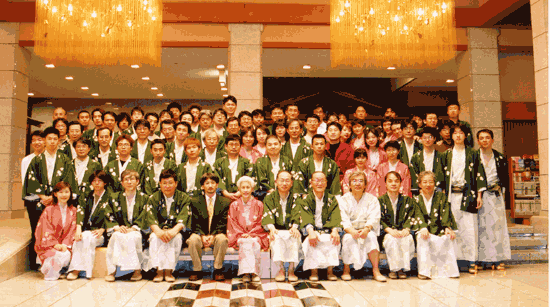
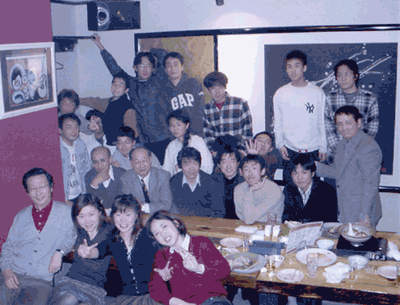
藤井義明先生の御退官によせて
生物化学研究室 十川和博
さる7月に札幌でおこなわれた第14回Microsomes and Drug Oxidations国際シンポジウムで、特別に藤井先生の業績を讃えるセッションが行われました。藤井先生のご講演のあと、何人もの日本人、外国人の研究者が藤井先生の功績をのべ、先生のご研究の深さ、偉大さを賞賛しました。藤井先生の業績は数多くありますが、チトクロームP-450に関する仕事を述べてみたいと思います。チトクロームP-450は謎めいていた、ミクロソームやミトコンドリアの膜に強く結合した酸化酵素です。よくわかっていなかったせいか、昔の教科書に載っているチトクロームP-450の記述は非常にあいまいなものでした。この深い謎の一端は、精製が困難で、また非常に多い分子種のため相互の分離もむずかしかったためであり、一般に近寄りがたい研究分野をつくっていました。日本では幸いチトクロームP-450の研究は盛んで、その層は厚く、その発見は藤井先生の先生にあたる、大阪大学の佐藤了先生と、その後、九州大学に移られました大村恒雄先生によってなされ、命名されたものでした。450 nmに吸収のピークをもつPigmentという意味でした。新しいタイプのヘムタンパク質です。藤井先生はこのチトクロームP-450にまつわる問題を解決すべく、まったく新しい技術でありました、遺伝子クローニングをこの分野に導入されました。当時マイナーなmRNAのcDNAクローンを分離する技術は確立されておらず、試行錯誤の繰り返しであったそうです。藤井先生は、トランスレーションアレストという方法でこの問題を解決され、これを駆使したスクリーニングによって、世界で最初にフェノバルビタールで誘導されるチトクロームP-450のcDNAをクローニングされました。東京で開催されました第5回Microsomes and Drug Oxidations国際シンポジウムで、この仕事を発表され、チトクロームP-450研究でのマイルストーンと絶賛されました。日本のチトクロームP-450研究の伝統が、藤井先生によって継承された瞬間でありました。その後共同研究者もふえ、もう一つの代表的な薬物代謝のチトクロームP-450である、メチルコランスレン誘導型が川尻要先生により、ステロイドホルモン合成のチトクロームP-450が諸橋憲一郎先生により、性特異的チトクロームP-450が吉岡秀文先生により、脂肪酸オメガ酸化のチトクロームP-450が松原修一郎先生によって次々とクローニングされました。これらの研究は藤井先生が確立されました方法に則って行われ、藤井先生の研究室はチトクロームP-450のメッカとなったわけです。その後、藤井先生はいくつもの大きな仕事をなされましたが、紙面も尽きたようですので、次の機会に譲りたいと思います。
藤井義明先生の思い出
阿部 比佐久
化学同窓会から何かを書いてくださいと言われて正直困ってしまいました。 藤井先生は真面目と言いますか、家から大学への往復でひたすら研究に励んだといった印象が強く残っています。朝の一番乗りは私が先といった時期もありましたが大半は藤井先生が先であったこともその一端を表しています。その藤井先生が、頭から足先まで巨人ファンというのは私には意外にも思えましたが 巨人ファンというのはあの長島茂雄と同世代と言うだけではなさそうなのです。(ちなみに私は巨人大嫌いです。)そうした藤井先生もスポーツはあまりなされませんでした。研究室では例年3月にスキー旅行がありましたが、藤井 先生は温泉に浸るだけでスキーはされません。腰痛のこともありましたのでそ の方がよかったのかもしれませんが、そのうちにお仕事の忙しさもあって一緒に行かれる機会も無くなり、”ボス”の参加しないスキー旅行の計画も立てにくくなって、有志だけになり事実上消滅状態となりました。
藤井先生が東北大学に来られた頃の1988年は、日本の大学で初めてといわれ るネットワーク網のTAINSが運用されました。まだネットワークについての認識が広がっていない頃でしたので利用する雰囲気も弱く、友人から古いHUB を もらい接続して通信環境をとりあえずつくりe-mail , database 検索などができるように整えました。藤井先生もパソコンの必要性を感じつつも取りかかるにはハードルが高かったのでしょうか少し時間を要しましたが、外国の研究 者はもちろん、いわゆる周りからも e-mailの要請が強まり、藤井先生も積極 的に活用すべく教授室にパソコンを置くことにしました。また、コンピュータ のハード、ソフトの進歩は学会発表や講演、講義で使うスライド作成が容易になりました。作ることが容易になったということは間違いや手直しなど修正も 容易になったのでぎりぎりまで言われることが増えたのには辟易しました。東北大生協にも次の日に受け取れるように現像所と条件を整えてもらったりしましたし、他のところでは2時間仕上げ店も現れました。ここで白状しますが、 この2時間仕上げは藤井先生にはしばらく隠していました。このようなこともあったので、藤井先生の最終講義のときにはPC−液晶プロジェクターの使用 をお奨めし、多少強引にお願いしました。藤井先生にはスライドの現物が無い状況で講演の流れを考えなければならないために辛いことになったと思います。結果としては、藤井先生も当日まで手直しができ、私も強迫観念にとらわれないで準備できましたので結果良しだったと思います。
藤井先生の研究の主体でもあったチトクロームP450を出発点に遺伝子の発現 制御、誘導機構の解明などに広がりました。また、アリルハイドロカーボン受容体(AhR)の cDNA クローニングに成功し全一次構造の解析を行いました。 AhR はダイオキシンに対して強い結合活性を有したことや他の外来異物による発癌や奇形の誘導、免疫細胞の分化、生殖機能に深く関わっていることも最近 明らかになっています。これらの研究に末端で微力ながらお手伝いできたこと を大変光栄に思います。まだまだ研究が続いておられるようですが、奥様とのゆったりした時間もつくられてお元気にお暮らし下さい。そして、ますますのご健勝お祈り致します。
ありがとうございました。