ボケ老人の独り言
森田 昇
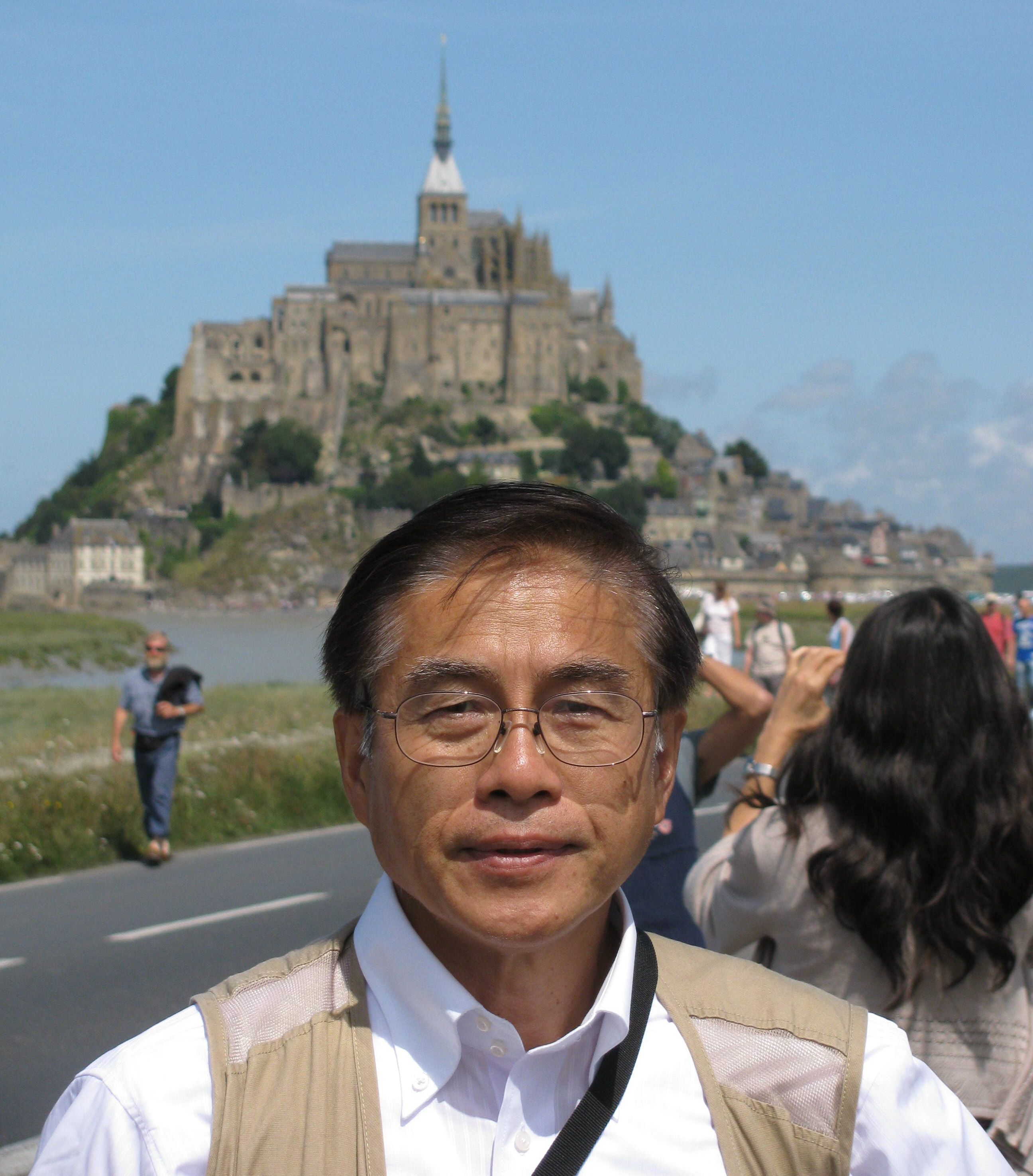
平成21年3月無事退職し、昔でいう隠居生活に入りもう半年を過ぎようとしております。
私は、第二次世界大戦の終わった次の年、ゼロの時代、昭和21年1月の生まれですのでボケ老人には覚えやすい時に退職したなと思われます。
私が東北大学理学部に入学したのは東京オリンピックの開催された年、昭和39年4月でした。現在では建て替えと100周年記念事業などで完全に建物の面影は残っておりませんが、そのころ川内に教養部があり米軍兵舎を利用して2年まで教養教育が行われていました。そこで我々の東北大生活が始まりました。自然科学を学ぶ上で重要な物理、化学、生物、地学の学生実験はまず講義で知識を詰め込み、それらを実験で実証していくという長年培われてきた考えの教育法にのって、1年の後期から2年の前期にかけ、それぞれ1週間に一回、午後1時から4時過ぎまでの時間に開講されておりました。(現在では教科合わせた実験の一部が半年週1回で開講されるようになってしまっています。自然科学の研究において実験によって証明しなければならないことを考えると実験の駒数をこのように減らしてしまうことはこれからの大学の自然科学の教育上非常に大きな問題です。)私は高校の教員免許を取るつもりだったので、その中の物理、化学、生物の実験の単位を修得しました。大学はその頃学部別に入学していたので、1年の終わりに学科が決められる制度になっていました。ゼロの時代に生まれ育った私はその時、化学を学んでおけば、社会に出ても化学の知識や技量を生かして、"飯が食っていけると"考え、化学を選びました。3年に進学してから現在大学の本部になっている片平化学教室で学部教育を受けるようになり仙台の街の中心で学生生活を色々な面で楽しみながら送ることができました。4年になって、私の研究は反応有機化学講座(北原善男先生)の助手をなさっていた加藤忠弘先生の指導のもとで生理活性をもつジベレリン等の合成をはじめました。具体的にはその頃大学院博士課程2年の音谷登さんの手ほどきで音谷さんの研究のお手伝いからら始まりました。博士課程2年の白幡公勝さんは秋田蕗の苦み成分から単離した化合物が珍しいスピロラトン構造をもつことを明らかにし、バッケノライドと命名しました。次の段階としてその合成を始めていました。4年の後半ではその手伝いをして卒業実験は終えました。バッケノライドの合成は今世紀になって報告されました。
この頃大学院の入学定員は学部の学生数の半分なのでかなり真面目に入学試験勉強をしなければならない時代でした。さらに、まだ語学の試験に第二外国語も試験範囲に入っていましたので4年の夏のドイツ語の入学試験勉強が大変だったことが思い出されます。
これが我々の学生時代受けてきた教育の1例です。現在はこのようなものから考えるとかなり異なった、いわゆるゆるい基準で大学教育が行われるようになってしまっていますが少し知恵を出して改善していかなければならないと思われます。
大学院に入学した時、反応有機化学講座の助教授の村田一郎先生が大阪大学の教授として栄転され、そのあとに合成有機講座の助教授の浅尾豊信先生が移ってきました。修士課程1年の工藤義彦君、種村満君と私の3人はたぶん教育上から先生がそうなさったのだろうと考えておりますが、将棋の駒のように研究室内の部屋を移動させられました。その結果、私はたまたま浅尾豊信先生の部屋に移ることになり、それ以来浅尾先生の指導で天然物化学や非ベンゼン系芳香族化学などの有機化学はもとより、色々な指導を受け続けることになりました。
大学院修士課程2年の時、大学紛争がおこり、教養部での投石や、片平地区の学内での学生のジグザグデモなど目のあたりにしました。この後遺症が博士課程3年のときすでに川内の教養部の教授になっていた浅尾先生の所へ助手として赴任、その後東京工業大学―シカゴを経てまた東北大教養に戻り、平成に入るまで助手として理系の学生の学生実験の指導と非ベンセン系芳香族化合物の合成、構造、化学反応性の研究を続けてまいりました。教養部が廃止され学部一貫教育がされるようになり川内北で行われる教養教育も全学教育と呼ばれるようになり、教養部にいた教職員の大部分は理学部等学部へ分属し私もその一人として古巣の化学教室に戻って参りました。その後16年の間に大学院重点化が行われ大学の教育の主体が大学院教育になり学部から研究科に教育の主体が移りました。さらに独立法人化され組織が官から民に移されました。我々が注意しなければならないことは、このような変化によって起こった結果に対する評価もせずに次々行われていることです。大学職員も独立法人化で公務員の教官から民間の教員になりました。その後大部分の助手が助教、助教授が准教授へと呼び名かわりました。しかし、このような変化は責任が増えたにもかかわらず、手当のなどの変動はない変化です。このような変化では組織や呼び名が変わっただけで大学人の研究や教育活動にプラスに作用しているのか、疑問に思えてなりません。大学の変革は大学人の知恵と努力によって大学人が主体的に責任を持ってなすべき時期に来ているのではないでしょうか。
学生時代を入れると約40年以上の長い間東北大で教育と研究生活のチャンスを与えられたことに幸せを感じております。これかれはなるべく今までやれなかったことだけをして気ままに生きていこうと思っております。清貧の生活ならば犬3匹(私とチコとテン)、充分暮らせるじゃないか?現在の私の心境です。
最後に現役時代の化学教室でお世話になった先生やその他の皆様のご厚情を感謝しつつ、化学同窓会会員の皆様のますますのご健勝とご活躍を祈念して筆をおきます。
―記述に誤りがあった場合は年のせいと考え、お許し下さいー 森田 昇
森田 昇先生のご退職によせて
弘前大学大学院理工学研究科 伊東 俊司
森田先生、ご退職おめでとうございます。
森田先生は、その当時、教養部の浅尾先生のもとで助手をされておられました。そこへ私が研究生として、お世話になったのが始まりです。
浅尾先生は、教養部長やら評議員などを歴任されており、教授室兼用の実験室では、もっぱら森田先生に実験の指導を受け、一緒にさまざまな有機合成の実験を行うことになります。森田先生は、当時、非ベンゼン系芳香族化合物の鉄カルボニル錯体やフルバレン構造に興味を持たれていたようでしたが、私にはそれらの研究をさせることなく、かなり自由に研究をさせていただきました。その当時、ひょんなことから始まったアズレンの研究が、今日までつながることになる研究に発展することになるのも先生のおかげと感謝しています。教養部当時の時間の流れが今日に比べ、ゆっくりと流れていたようなに感じられるのは、朝から、夜遅くに帰宅するまで、森田先生と自由奔放に研究をさせていただいたことによるものからかもしれません。また、森田先生ご自身が混ぜては分離、混ぜては分離の根気のいる有機の合成実験を楽しまれているのを間近に見てきたことによるものからかもしれません。
そんなどこかのどかだった教養部も終焉を迎え、理学部への配置換えを経て、新生、森田研にも何人かの学生がやってくることになり、新たな研究室の立ち上げが始まります。なぜか立ち上げ当初から、先生の自由奔放なお人柄に惹かれてか、森田研にはうらやましいほどの個性豊かで優秀な学生が集まってくることになります。その当時の学生たちが、今日もなお、年に一度、遠く沖縄や四国をはじめとして、全国各地より集まることになるのも先生のすばらしい研究室運営の賜物と思えて仕方がありません。当時、先生は夏の暑い日には、市場によってスイカを買ってきたと、実験用の氷で冷やして、学生に振舞ったり、そうめんをたくさんゆでて、学生に振舞ったりと、研究面以外においても、型破りのお人柄を発揮していました。
振り返ると先生にお世話になることになってから、もうかれこれ20年以上にもなります。森田先生、長い間大変お世話になりました。森田研の立ち上げ当初から、まさに「森田研黄金時代」と呼ぶにふさわしい時期を、過ごすことができたことに深く感謝しています。また、弘前大学に転出後も大変お世話になり、感謝してもしつくすことはできません。
実際に研究室を受け持つようになり、改めて森田研のような人間味に溢れて活力のある研究室作りの難しさを感じるようになりました。先生のお人柄によるすばらしい研究室の終焉は残念ですが、お体にご自愛いただき、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
先生どうもありがとうございました。
森田先生のご退職によせて
横山 隆二
森田先生、御退官おめでとうございます。
ただ、森田研究室へ遊びに行く機会がなくなると思うと残念で仕方ありません。
森田先生に初めてお会いしたのは、配属のための研究室紹介のとき。"温厚"で"話好き"な教授というのが森田先生に対しての第一印象でした。研究室選択にあたり、教授や研究室の雰囲気を第一に考えていましたので、森田先生のお人柄に触れ、森田研(構造有機化学研究室)への配属希望を即決したのは言うまでもありません(研究内容には興味なかったのかとお叱りをうけそうですが、全く興味なかったので仕方ありません)。
構造有機化学研究室では、当時助手をしておられた伊東先生(現・弘前大学教授)や学生にも恵まれ、アットホームな雰囲気で自由に研究生活を送ることができました。また、講座旅行・芋煮会・ヨットレースや仮装マラソンなど、イベントへの参加もよい思い出になっています(マラソンは準備したものの雨天中止)。これも一重に森田先生のお陰だと思っています。
研究面においては、指導教官として優しく、また熱心に様々なことをご指導頂きました。特に思いで深いのは原料合成。配属の初日にも関わらず、夜の12時過ぎまで続いた「ジシクロペンタジエンの熱分解」。毎日毎日、10L分液ロートを振ってはポリバケツで反応させて合成した「トロピルカルボン酸クロライド」。また、仙台を離れる2, 3日前まで作っていた大量の「トロポロン」。当時は不満もありましたが、今となっては良い経験だったと思っています。
森田先生との思い出を挙げればきりがないのですが、その中でも私にとって外すことのできない「2000年夏のバイク事故」について触れたいと思います。
その日、実験していたことだけは覚えているのですが、目が覚めると森田先生の家。「何処?何故、森田先生の家??」という感じでした。森田先生によれば、帰宅途中、タクシーにはねられて救急車で運ばれたとのこと。頭を強く打っていたので、医者としては一人で帰られせる訳にはいかなかったらしく、森田先生に引き取って頂いたそうです。
何故、森田先生が引き取ったのか?記憶にはないのですが、自分で先生の連絡先を知らせたそうです。無意識のうちに森田先生を頼ったのには驚きましたが、それだけ信頼していたからだと思っています。事故の折には、奥様をはじめ、ご家族にも大変お世話になりました。この場をお借りして深くお礼申し上げます。
森田先生には、学生時代はもちろんのこと今でもお世話になりっぱなしです。本当にありがとうございました。また、これからも何かと心配をおかけすると思いますが、宜しくお願いします。
最後に一言。
恒例の「温泉旅行」、続けますので参加してください。