第4回日本物理学会若手奨励賞と電子スピンサイエンス学会奨励賞を受賞して
筑波大学図書館情報メディア研究科 講師 水落 憲和
(4月1日より所属は筑波大学数理物質研究科に異動となります。)
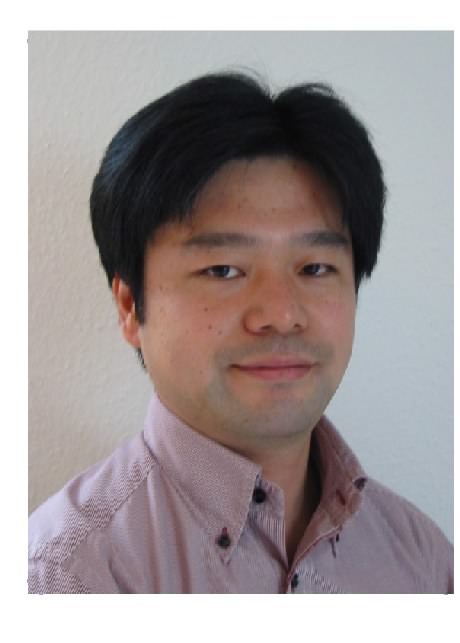
この度、第4回日本物理学会若手奨励賞と電子スピンサイエンス学会奨励賞を賜りました。今回の受賞に関する研究は主にシュトゥットガルト大学のWrachtrup教授研究室及び産業技術総合研究所山崎グループとの共同研究によるものです。両グループの皆様にはこの場をお借りして深く御礼申し上げます。
振り返ると東北大学で博士を取得して仙台を離れてからもうすぐ10年になり、まさに"光陰矢のごとし"を実感しています。大学院時代は多元物質科学研究所の山内先生の研究室で山内教授、大庭准教授らと共に電子スピン共鳴法を駆使してフラーレン化合物の光励起状態を研究していました。博士取得後につくばに来てから、研究テーマはシリコン、炭化ケイ素、ダイヤモンドなど固体材料を扱うものとなりました。固体材料研究は物性研究といった学術的な研究から応用研究まで幅広い研究があり、また学際的な研究領域でもあります。材料合成や微細加工において化学反応が重要な役割を演じたり、高品質化や特殊なナノ構造などを作製することにより様々な面白い物理現象が現れたりします。従ってつくばに来てから研究分野は物理化学のみならず、物理や工学など幅広い分野になっていきました。そんな中、ダイヤモンドの研究をしている時に出会ったのが、窒素‐空孔複合体中心(NV中心)で、この研究の成果が今回の受賞につながりました。
量子暗号通信や量子コンピューティングという言葉を皆さんもお聞きになったことがあるのではないかと思います。これらにより絶対に解読不可能な暗号通信や、既存の計算機を遥かに凌ぐ超並列計算機の実現が期待されています。量子情報科学の近年の発展は目覚ましく、理論も様々ですが、量子の特異な性質を生かすために単一の光子や単一のスピンを扱うことが原理的に要求されています。光子は通信に適し、スピンは計算や記憶に適しており、単一のそれらを量子暗号通信や量子コンピューティングに使おうというわけで、世界中で非常に活発に研究がなされています。
近年、ダイヤモンド中のNV中心が単一光子源、量子レジスタ、量子メモリ等の量子情報素子源として注目されています。理由としては単一のNV中心を光学的に観測する技術が確立しており、そのNV中心が持つ単一スピンを制御できるようになってきたからです。またNV中心のスピンは固体中のスピンとしては一番長く重ね合わせ状態(コヒーレンス)を保持できることが分かってきています。物理化学の分野の方々には単一分子の発光を観測する技術が既に確立していることはご存じの方も多いでしょうが、これが発展した技術をここでは用いています。単一のNV中心からの発光を観測することにより単一のスピンの情報を読み出しています。
量子情報素子研究には情報を扱うビット(量子ビット)の数を如何に増やすかという課題があります。私は核スピンを持つ同位体13C(I=1/2)の量を増やしたダイヤモンド試料を用いれば、量子ビット数を数量子ビットに増やせると着想し、産業技術研究所のグループ、ドイツのグループと共同研究を行いました。核スピンは格子や電荷といった他の自由度との相互作用が小さいために重ね合わせ状態(コヒーレンス)を保持する時間(T2)が非常に長く、良い量子ビットとなりうることは1990年代後半から盛んに行われていた核磁気共鳴法による研究でよく知られていました。一方で外界との相互作用が小さいことは、核スピンに容易にアクセスできないことも意味し、これまでは多数の分子からなるアンサンブル系での研究がなされているのみでした。そこで量子情報で重要な役割を担える単一核スピンを、単一NV中心の電子スピンを介して光学的に検出し、操作しようというわけです。私は平成18年度から20年度までに3回にわたって半年間ずつ、合計1年半ドイツのシュトゥットガルト大学に渡航し共同研究しました。その結果、量子もつれ状態と呼ばれる量子情報で中心的な役割を演ずる状態を、固体中の室温で初めて実現しました。それまで固体では超伝導素子を用いて2量子ビット間での実現が極低温でなされていましたが、室温でしかも3量子ビットまで拡張できた点は特筆すべきです。さらに重ね合わせ状態(コヒーレンス)が壊れる機構の解明や、室温で電子スピンのT2を1ミリ秒以上に伸ばしたことなど、NV中心の持つ高い潜在能力を示すこともできました。
最近は実験装置を自ら立ち上げ、単一NV中心の研究を筑波大でもできるようにしました。単一のNV中心などの発光中心は学術的な関心に加え、優れた特性ゆえに幅広い応用が期待されています。量子情報といった量子物理の深遠な性質を扱う分野のみならず、生体内のプローブや超高感度の磁束計といった幅広い分野でも非常に有望視されています。エキサイティングなテーマがたくさんあり、そのような研究に携われることは幸運だと感じています。今回の受賞をバネに、これからもさらに研究を発展させられるよう努力していきたいと考えております。今後もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、東北化学同窓会の皆様のご発展とご健勝をお祈りいたします。
大気環境学会地域奨励賞を受賞して
花石 竜治

この度、大気環境学会地域奨励賞を受賞し、平成21年9月に、慶應大学日吉キャンパスで行われた同学会の総会で表彰を受けました。
私は大学院博士後期課程中退後、青森県に就職し、青森県環境保健センターに勤務しております。最近は十和田湖についての調査研究とダイオキシン類調査を担当しています。
学会賞授賞の理由は、大気環境科学の分野の「ケミカルマスバランス(CMB)法」という数値計算手法について研究を行ったこととされています。小生らは、米国環境保護局公認のソフトを市販の表計算ソフトのマクロに書き換え、利便性を高めました。
大学院学生時代の大半を旧反応研の研究室(岩泉研、山内研)に所属しましたが、当時得たコンピュータ技術が、仕事を進める上で非常に有用です。数値計算はもちろん、測定データが膨大に存在する調査もののような研究では、プログラミングの技術なくしては取り組むことができません。
普段の仕事として、有機無機問わず、多種多様な環境汚染物質を標的とし、現場での試料採取から、分析まで仰せつかっています。業務の支えとなっている化学の広範囲かつ良質の基本を授けてくださいました化学教室には、深くお礼を申し上げます。また、分析屋として、機器分析やデータ解析などを億劫がらずに行えるのは、物理化学の研究室で訓練を受けた成果と思っております。
少し前までは、学生時代の磁気共鳴の研究に関して当時未解決だった理論的側面を、私事の研究として、岩泉正基名誉教授の御指導のもと取り組んでいました。その成果の一部は一昨年出版されました(R. Hanaishi, J. Magn. Reson., 193 (2008), 119-126) 。そういう経緯もあったのですが、学会賞を受賞してからは、環境科学こそが自分のライフワークであり、一人の人間として生涯を捧げるべき仕事と実感し、学生時代から卒業しました。
受賞に至りましたのは、御指導御鞭撻を賜りました本県の上司、同僚のお蔭であり、今後ますます精進を重ね、本県の環境保全行政に、微力ながらも力を尽くす所存でおります。
末筆ながら、同窓会のますますの御進展を祈念いたし、受賞の御報告といたします。