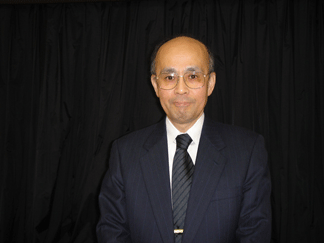
化学教室の思いで
菊池康夫
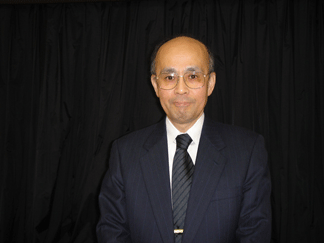
平成17年(2005年)3月に停年となり、東北大学を退職した。大学の組織のうえでは生命科学研究科に属していたが、最後まで化学教室で過ごすことができた。学生時代とその後もずっと長い間にわたって過ごした化学教室への愛着はつよく、心の中では化学教室で定年を迎えたと思っている。退職の直前には第一講義室に最終講義という場まで設けていただき、お集まりいただいた大勢の皆さまのまえで研究生活を振り返ってお話させていただくこともできた。それからあっという間に一年が経ち、同窓会報に寄稿する機会をいただいたままで過ごしてしまった。ここで、また化学教室での思い出を綴ってみることをお許しいただきたい。
化学教室まで
私が東北大学理学部に入学したのは昭和37年(1962年)である。川内の教養部キャンパスはアメリカ進駐軍のキャンプ地跡で、高い塔の教会や白ペンキ塗りの兵舎が図書館や教室に利用されていた。いまからみれば粗末な環境だったかもしれないが、広々として明るいキャンパスに思えたのは社会全体が豊になるまえのことだったからだろう。
当時は理学部の入学者は一括して合格させ、一年の後に進路(専攻)を決める方式だった。私は化学を志望したが、幸いなことに、この年度から化学第二学科が新設され化学の定員は35人から70人に倍増した。化学は社会の未来を拓く産業として人気があり、志望する学生が多い時代であった。あとになって私は生物化学への道を選んだのだが、そのときも、化学の方法と「いのち」を支える仕組みを結びつけたいと思ったからだった。その思いは私のなかで湧いたと思っていたが、DNAの二重らせんが提唱されてから十年が経ち生命の謎が解けはじめる期待がふくらんでいた時期でもあった。自分で決めたことではあったが知らず知らずのうちに世間の雰囲気に染まっていたのかもしれない。しかし、どちらの選択も私の性にあっていて最後まで楽しい時を過ごすことができた。
片平の化学教室
三年生になって化学科の学生として片平丁の化学教室に進学した。堂々とした建物はいかにも歴史のある学科と思わせるに十分だった。この建物はいま、外観はそのままで、大学本部として使われている。ここで学んだものには懐かしい場所である。内部はすっかり改装されたのだろうが、しかし、当時でもすでに老朽化が指摘されていた。魯迅も学んだという歴史ある階段教室は坐り心地のわるい木の長椅子だったし、学生実験室のドラフトは天井にあるガスバーナーに点火してその上昇気流で排気するものだった。私たちの進学に合わせて増築された化学第二学科の実験室には新しい装備が備えられ、モーターで排気するドラフトも付いていて、それがまぶしく思えた。そういう時代だったのだ。
化学教室での生活がはじまると「おとな」の仲間入りをしたと感じた。みな互いに「さん」で呼び合っていたのが新鮮だった。私たちも、講義で教わる先生にだけは「先生」だったが学生実験でお世話になった助教授や助手の先生にはなれなれしく「さん」で呼びかけて平気だった。学生実験ではどんなに遅くまでかかっても付き合ってもらったし、時間外には研究室におしかけて雑談したり、研究室の実験装置に目を見張ったりした。
春の八木山野球
春には八木山野球という行事があった。八木山の市営球場はもう無く、動物園の一部になっている。その昔ベーブルースがホームランを打ったという球場だったが、ちょっと大きいフライならホームランになってしまう狭い球場であった。野球の道具をリヤカーに積んで片平丁から八木山まで運ぶのは三年生の役目だった。なぜリヤカーだったのだろう? ひとりくらいクルマをもっていなかったのだろうか? ともかくリヤカーで運んだのだ。ラインを引いて準備ができる頃には人も集まってきて、学年ごとのチームと教職員チームの対抗試合が始まる。ずっと昔には野球のルールを知らない人もいて、打ったら三塁に向かって走ったとか、「一度も振らないのに三振とはなんだ」と文句を言ったという伝説を聞いてはいたが、さすがにそういうことはなかった。野球を楽しんで、昼食時には新三年生の紹介があって、また野球をして、夕方にはリヤカーを引いて帰った。この行事は春のスポーツ大会として今も続いているし、野球はのちに講座対抗の野副杯野球大会になった。
卒業祝賀会
いまは国際センターで行われている祝賀会である。教室の全員が出席して卒業生を祝う会で、卒業生や新任の先生のスピーチがあるのもいまと変わらない。はじめて出席したときにおどろいたのはひとりひとりが座る席が用意してあって、ウェイトレスさんがお皿にのった料理を運んできて、ナイフとフォークで食べたことだ。書いてしまえばそれだけのことだが、いまでも思い出すのだから私にとってはずいぶん緊張した事件(?)であったにちがいない。ナイフとフォークで食べる「洋食」といえばとびきり上等な料理と思っていたし、上手に食べる自信もなく周りに気を遣ってビクビクしていたのだろう。いま思い出すとおかしいというより懐かしい。この形式の祝賀会はやがて終わりになった。学生の定員が増えて全員が着席できる会場がなかったためと聞いている。
ダンスパーティ
卒業祝賀会の前後に化学教室ダンスパーティがあった。卒業祝賀になぜダンスパーティだったのかはわからない。いつ、誰が始めたのかも知らない。その企画・実行は三年生の役目といわれてあまり違和感なく受け入れたのは当時の雰囲気のせいだろう。ダンスパーティが盛んだったのだ。パーティに行くには踊れねばならない。そこでダンス講習会も盛況だった。いろいろな運動部が講習会とパーティをセットで企画すると人が集まって活動資金が調達できたのだ(活動資金のために券を売りまくって人を集めたのかもしれない)。同級生のなかにはその事情に通じている者がいて、会場の設定とか人脈をたよって「適当な人数」の女子大生に「招待券」を配ったりする。化学教室の女性は少なかったし、お相手を同伴できる卒業生は少なかったからである。私は先生の部屋を訪問してご寄付をいただく役回りであった。慣例になっていたせいだろうが、500円〜1000円を気前よく出していただいた(当時の物価からみるとこれはとても大きい金額であった)。
当日は学生、院生、先生をはじめ、図書室や事務室のみなさんも集まって大変な賑わいだった。卒業を機会に背広とネクタイを新調するので、ふだんのよごれた白衣姿とはちがってみなめかし込んでいる。どこでおぼえたのかダンスも上手だ。奥様を同伴された先生が軽やかに踊るのをみて目を見張ったりした。結婚したばかりの先生や院生が仲間に囲まれてひやかされたりするのもこういうときだ。私たちは世話役だから準備や受け付けの仕事があって、それがすむと会場の片隅で盛況のダンスを眺めていた。なかにはお客様の女子大生の手をとって踊れるものもいた。お客様を退屈させないのも役目のうちであったのだが、そういう「教養」のない者はただ眺めるしかなかった。一年後には私たちが卒業生の立場になる番だ。それからの一年は卒業研究で実験が忙しくなるなかでダンス講習会をひらいたりして「祝ってもらうのも大変」という経験をすることになった。
しかし、この習慣もまもなく消えることになった。盛んだったダンス熱が下火になってきたことも原因だろう。化学教室の学生定員が35名から70名に倍増し、それにつれて講座も増えて大きくなる過渡期だった。こぢんまりした集団で続いてきた行事も維持が難しくなったし、「卒業祝賀になぜダンスなのだ」という疑問も大きくなったためだろう。
大学紛争
全国的に盛り上がりを見せた学園紛争の波は東北大にもおしよせたとき私は大学院生になっていた。世に言う「70年安保」である。はじめは「大学の自治、学問の自由を守れ」、「学生の声を大学に反映させよ」ということかと思われたが、いつの間にか「日米安保条約反対」から「アメリカ帝国主義粉砕」まで様々なスローガンが並べられた。大勢の学生がヘルメットに覆面姿で気勢をあげ、学生の集団同士が長い棒(ゲバ棒)で殴り合ったりした。それぞれの集団を応援する教職員もいた。やがて建物の「バリケード封鎖」、それを解除する「機動隊導入」があったりして、川内キャンパスだけでなく片平丁でも騒然とした空気になった。
化学教室でも何度も「集会」という議論の集まりが開かれた。ふだん教えていただいている先生を語気鋭く糾弾する学生がいたし、先生がたじたじとなって返答に窮することもあった。「産学協同」路線は大企業に奉仕し人民を搾取する研究として槍玉に挙げられたし、「レーザー」は殺人光線と同義語で軍事研究の片棒担ぎとレッテルを貼られる雰囲気であった。騒々しく、とげとげとしい空気だったが化学教室が無法地帯と化し乱闘騒ぎが起きることはなかった。多くの危険薬品をかかえる化学教室を守らねばならないという思いは共有されていたし、外の学生集団にも通じたものと思われる。
化学教室での議論も堂々巡りで出口のないように見えたが、やがて化学教室の問題に集約されてきて「教官会議」や「協議会」を新たに設け、「化学教室運営規則」もつくることになった。その実現まではまだ長い道のりだったが、大筋で意見も一致したし、こういう議論はひと休みしたいという雰囲気になった。そのとき開かれた「一般雑誌会」は久々の学術集会で、それまでまとめ役だった中西先生が「今日は化学の話ができる。わたしはそれが本当にうれしい」と前置きして昆虫変態ホルモンの研究を紹介された。
おわりに
「日和見」とか「ノンポリ」とかいわれた私の目に映ったのはほんの表面のことでしかない。それでもいま思い出すとあのエネルギーはどこから湧いたのだろうと不思議だし、大学の外も内も大きく変わったことに気づく。30年の年月が経過したのだから無理もないことだ。私の化学教室での生活も終わり、やがて懐かしい思い出に変わっていくことだろう。化学教室はこれからも社会に即して変化しながら研究と教育の実績をあげていくにちがいない。長い間おせわになった化学教室に感謝し、いまご活躍中の皆さまのご多幸とご発展を祈っている。

