赴任の御挨拶と私の目指す天然物化学
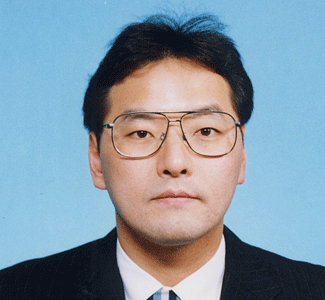
赴任の御挨拶と私の目指す天然物化学
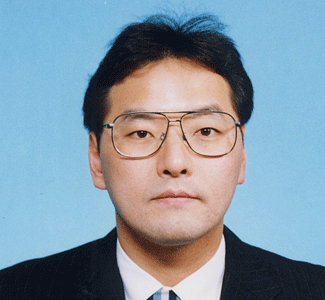
上田 実
初めまして。
私は2月1日付けで有機化学第一研究室の教授に就任致しました上田 実と申します。有機化学発祥の地、仙台に来て早くも5ヶ月が過ぎようとしております。化学教室の皆様の御支援のおかげで、ようやく実験環境も整備されつつあります。今は前任地からついてきてくれた学生さん達と研究をしておりますので、10月に東北大学の学生さん達が配属されて、研究室がどのように変化していくのか、楽しみにしています。
さて、少し自己紹介をしてみたいと思います。私は名古屋生まれで、かろうじて東京オリンピック後、幼少の頃に大阪万博を経験した世代になります。大学、大学院、就職に伴って、神戸、名古屋、横浜と移り住みまして、その土地の雰囲気と生活を満喫しつつ、仙台にやってきました。私の専門は天然物有機化学ですが、私がこの分野を志したのは、そもそも大学2年の時に拝聴した中西香爾コロンビア大学教授(東北大学名誉教授)の御講演の影響が甚大であったかと思います。当時の私は、有機化学反応機構の美しさと多才さに魅せられおりましたが、「生物現象に化学でアプローチする」ことの見事さに一気に引き込まれました。中西先生は、今でも私が最も尊敬する有機化学者です。その後私は、中西先生と同門の故平田義正教授門下の故後藤俊夫名大教授の研究室の門を叩き、ヤグルマギクの超分子複合型花色素プロトシアニンの研究で学位を取らせていただくとともに、「動的天然物化学」というアプローチについて大いに薫陶を受けました。学位取得後、直ちに山村庄亮慶應義塾大学名誉教授の下で、当時難攻不落と言われた「オジギソウの刺激伝達物質」に関する研究に従事しました。学位論文のテーマはWillst?tter以来80年間未解決、オジギソウのテーマも80年間未解決ということで、研究者としてのスタートラインにおいて随分無茶なテーマに連続して取り組ませて頂き、なんとかモノにしてきたことが、自分の研究『勘』に大きな影響を及ぼしているように思います。またこれらの期間に、生物現象を見るための「目」を養えた事が貴重な経験でした。その後、慶應で助教授として独立講座を主宰した後に、本学化学教室に赴任して参りました。
現在の研究は、ダーウィン以来の謎といわれる「植物の運動」という生物現象に関する天然物有機化学です。天然物有機化学と申しましても、私のアプローチは化学に限らず必要な方法は何でも使うというやり方ですので、植物栽培から、クローン培養、「モノ取り」、超微量構造解析、合成、各種化学分析、顕微鏡切片の調製と観察、タンパク質の分析と精製まで、なんでも自分達でやります。これは、生物現象の解明には、化学を軸とした総合科学的アプローチと全体を見渡すことができる視点が必要であると言う私の信念に基づくものです。
生物が生産する化学物質を研究するという行為は、「自然の謎に触れる」という人間の好奇心の源泉を刺激するものです。ポストゲノム時代といわれる今日、遺伝子情報を入り口とするゲノム科学とは逆に、生理活性物質を用い、生物現象を入り口として生命現象へアプローチする天然物化学的方法は、ゲノム研究と相補的足りうる重要な手法となる可能性を秘めています。トンネルを両側から掘るように、両者のアプローチをあわせれば、生物現象からゲノム情報までを一本のストーリーとして語ることができる日が遠からず来ることでしょう。私は、かつてよりも深く「自然の謎に触れる」ために、ポストゲノム時代の「動的天然物化学」を目指して研究を進めると同時に、生物(現象)を観察する目を持った化学者を育ててみたいと思っています。
独り言
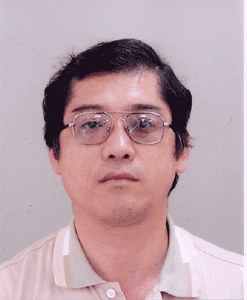
錯体化学講座 山下正廣
私は九州の唐津で生まれ、次第に北上をしながら50年かけて仙台の地にたどり着いた。小さい頃には仙台がどこにあるかも知らなかったし、自分が仙台に住むことなど全く予想もしなかった。まさに青天のへきれきである。東北大学で、研究場所としては7ヶ所目であるし、教授になってから数えても3ヶ所目である。九州人は、元来は農耕民族であるはずだが、私の体のなかには狩猟民族の血が流れているのかもしれない。いつも新任地に移ると3年くらいで慣れ、5年もすると飽きてくる。おまけに、雑用が5年目くらいから山ほど来る。研究は5年で一仕事はできるので、5年目前後から他の研究場所を探して応募し始める。その結果7ヶ所も研究場所を変えたことになる。よくよく考えてみると、雑用もなく朝から晩まで研究だけに打ち込んだ時期は分子科学研究所でポストドクをやっていた1年だけである。ちなみにその時の指導教員は伊藤翼東北大名誉教授で、私は20年後に伊藤先生の研究室を引き継いだことになるわけで、これも何かの縁だと考えている。
研究は錯体化学であるが、特に「ナノ金属錯体の科学」(金属錯体を用いたナノサイエンスと言う意味で)と自分で命名して新分野の開拓を行っている。これまで、数十名の院生を卒業させ、また10以上の他大学で集中講義を行ってきたが、いつも最初に言うことは、「学問とは何ぞや!」である。意外とわかっていない院生が多いことに驚くし、教員でもわかっていない人が多いことには失望感さえ感じる。「学問」とは「新しい概念の創造」であることは疑う余地のないことである。しかし、それだけでは不十分である。もう一つ、大切なことは「新しい分野の創造」である。この二つのことをやって初めて学問をやっていると言えよう。この立場からすれば、今からナノチューブや酸化物銅などを研究することは学問以前の話と言えよう。ところが、ある研究会で、関東にある某大学の某氏は「研究とは体系化すること」であるといって信じきっていることには驚かされた。そういえば、彼はフラーレンの誘導体を必死に合成していることから、その大学では「学問」についてそのような教育をしているのだろうと推察された。これでは日本で一番の予算を文科省からもらっているその大学での研究費はまさにドブに捨てるようなものである。まことにお粗末な文部行政であるし、その大学の化学系では永遠にノーベル賞学者はでないであろう(何もノーベル賞をもらうことが偉いわけではないが)。
私の研究対象の金属錯体は、設計性に富んだ有機配位子と電子状態の多様な無機金属イオンから構成されているために、それらをうまく組み合わせることにより従来の無機化合物や有機化合物を越える機能性や物性が期待される。しかし、錯体化学討論会などでは、「金属錯体において初めての現象である」と堂々と発表している研究者がいる。まことに恥ずかしい話である。有機化学や無機化学で常識であることを「金属錯体」で始めて見つけたからと言って「科学」としてどれほどの意味があると考えているのだろうか?有機物、無機物、金属錯体などすべての化合物のなかで最高の物性です、初めての現象ですと言って初めて「学問」といえよう。多少、自慢話になるが私の合成した「強相関電子系ナノワイヤーNi(III)金属錯体」の三次非線形光学感受率はすべての物質で世界最高の10-4e.s.uを持っている。これはポリシランなどのバンド絶縁体の1万倍以上の大きさであるし、ポリアセチレンなどのパイエルス絶縁体の10万倍以上であるし、同じ強相関電子系の酸化物銅の1万倍以上であり、世界最高である(Nature, 405,929(2000))。永遠に他人には破られない記録であろうと密かに自負している。このような楽しみを与えてくれる「金属錯体」が大好きで、30年ちかくもこの分野の研究を続けることができる秘訣かもしれない。