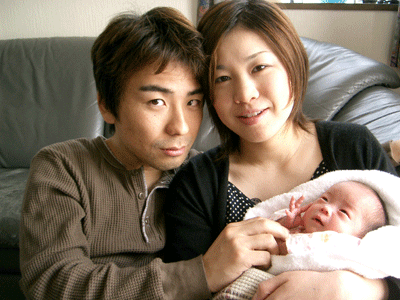
日本分析化学会東北支部奨励賞を受賞して
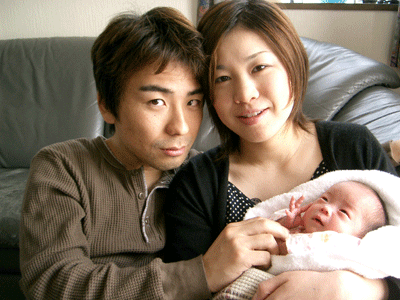
平成15年度理学研究科化学専攻分析化学研究室卒業生
現理化学研究所バイオ工学研究室 基礎科学特別研究員
吉本 敬太郎
今年の3月に日本分析化学会東北支部奨励賞を受賞しました。私のような浅学非才の凡人が,博士課程修了時にこのようなすばらしい賞を受賞できたことは,ひとえに,寺前紀夫教授をはじめとする分析化学研究室のスタッフ皆様の終始暖かい御指導があったからこそであると考えています。特に直接の指導教官である西沢先生には数え切れないほどの御指導と御助言を賜りました。本誌面をお借りいたしまして再度深く御礼申し上げます。
私は博士課程前期二年の課程(修士課程)を工学研究科の応用計測化学講座で過ごした後,博士課程進学の際に本研究科への転科を決意し,化学専攻分析化学研究室(寺前研)に三年間お世話になりました。今回の受賞の対象となりました研究課題は,核酸の一塩基変異を対象とする分析法の開発ですが,当時の研究室には核酸を本格的に扱った経験者が居なかったため,実験法や試薬調達に非常に戸惑ったことを覚えています。また,研究がある程度軌道に乗るまでは常に不安と隣り合わせの毎日で,正直,精神的に苦しかった時期が何度かありました。新しい環境下での研究生活は,想像していた以上に楽なものではありませんでしたが,一方で,私の研究の幅を大きく広げ,冷静に今までの自分を見つめなおす絶好の機会であったと思います。博士課程の後半部分では,悩み,また苦しむことで自分が大きく成長することに喜びを感じ,博士課程修了後の進路はどのような分野に飛び込もうかと日々考えていたほどです。転科が当時の最善の選択であったとは言い切れませんが,少なくとも私にとっては,人生の大きな転機の一つとなったことは疑いようがありません。
辛い時期も少なくなかった研究生活ですが,幸運にも友人などには恵まれており,研究がうまくいかない時期には同期のメンバーに忌憚の無い意見や助言を多くもらい,時には研究以外のことで楽しくバカ話をすることもありました。これがどれだけ私の励みになったことか,本当に感謝の言葉も見つからないほどです。学生時代に既に入籍済みであった妻にも研究上のイライラなどをぶつけていました。しかし彼女には,私が最も多忙な時期である内審査から卒業時期にかけて,入院×出産×引越しの三倍返しをされました。今となっては,彼女が妊娠中毒症と診断されて緊急入院した日のこと,翌日の内審査会の発表が散々だったことは良い?思い出となっています(内審査が散々だったことは,当然彼女にぶつけてやりました)。
卒業後,私は幸運にも研究を職業として続けられる機会に恵まれ,現在は理化学研究所のバイオ工学研究室で基礎特別科学研究員という職に就いています。本年度から家族も三人となり,公私に課せられた責任が日々大きなものとなっていることに少々戸惑いながらも,気持ちを一新し,初心を忘れず一層身を引き締めて研究に邁進いたす所存ですので,今後とも皆様の御指導と御鞭撻を賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。
加藤 雄一(平成15年度卒)
この度日本分析化学会東北支部より,「水素結合性リン酸イオン分析試薬の開発と機能評価」の業績で東北分析化学奨励賞を受賞する栄誉に恵まれました。受賞の報告にあたり,研究室配属時から辛抱強く御指導頂きました分析化学研究室・寺前紀夫先生,西沢精一先生に深く感謝申し上げます。またこの賞を受賞するにあたり早下隆士先生,内田達也先生(現東京薬科大学生命科学部),山口央先生の多大な御指導を頂いたこと,一方,本研究を進展させるにあたり御協力や御指導を頂きました能智公久博士(現富士写真フィルム株式会社),山下智富博士,重森一輝弁理士,吉本敬太郎博士(現理化学研究所)に,更には分析化学研究室の皆様に,この場をお借りして深く御礼申し上げます。
もう十年近く前の話になりますが,私は学部時代の座学を中心とした基礎化学の授業で疲れてしまい,これから先の研究者としての展望が全く描けない状況にありました。今になって思えば,私の発想が非常に貧困なせいで,授業と研究とをリンクさせることができず,また自分自身が消極的で受け身であったことに原因があったのだと感じています。
その発想が大きく変わったのは研究室配属時でした。寺前教授と西沢講師から非常にチャレンジングなテーマを頂き,自分の手で研究を進めることに,大きな緊張感と喜びとを感じたのを今でも新鮮に思い出します。また教授から頂いた「自分の研究が世界でどのような位置付けになっているかいつも意識すること」というコメントが,研究に対する緊張感や喜びを増幅させ,より大きな意味での「研究の楽しさ」も強く感じたことを覚えています。
一方,研究室に配属されて,研究というのはグループの力で進むのだということも勉強させられました。私のような若輩者が今回受賞できたのも,化学教室でのすばらしい同期や先輩・後輩達に囲まれ,刺激されつつ研究ができたからだと強く思いますし,そのような環境で研究生活の第一歩を始められたことに強い喜びを感じています。
今回受賞の対象となりました研究課題は「水素結合性リン酸イオン分析試薬の開発と機能評価」というもので,通常高極性環境下では機能し得ない水素結合性アニオン分析試薬が,スタッキングなどの協同効果を併用し,また分析場をうまく構築することによって十分機能しうることを幸運にも見出すことができました。本研究の遂行にあたっては,分析化学研究室に留まらず,他研究室の暖かい御協力あってのことであり,この場をお借りして感謝を申し上げます。特に配属当時から分析センター(現:巨大分子解析研究センター)の佐々木先生,近藤先生には無理難題ばかり持ちかけてしまいましたが,嫌な顔一つせず分析して下さり,その結果研究が大きく進展したことは忘れられない良い思い出です。
現在私はアカデミックの世界を離れ,トヨタの基礎・先端研究を行っている豊田中央研究所の研究所員として勤務させて頂いております。企業研究所での研究に対する考え方,進め方は大学の世界とはもちろん大きく異なっており,その感覚を掴むことに腐心しているところです。
しかしながら化学教室で研究させていただいた経験はこちらでも大きく生きていると感じます。化学教室の卒業生として恥ずかしくないよう精進しなくてはと,今本寄稿文を書きつつ気持ちを新たにしているところです。
名古屋に来てからは教授からの餞の言葉である「Enjoy your life」をよく思い返しています。配属された当時はこれを文字通り受け取っていましたが,今思い返すと非常に深い言葉だなと感じています。自分の研究人生を「楽しむ」為にはどうすべきなのか?,答えは出ないのかもしれませんが,悩みながらも楽しんでこれからの長い研究生活が送れればと思っております。
最後に今後とも同窓会皆様のなお一層の御指導と御鞭撻を賜りますよう,どうぞ宜しくお願い申し上げます。
大変乱文ではございますが,同窓会皆様のなお一層の御発展を祈念しつつ,受賞の報告とさせていただきます。このような場を与えていただきありがとうございました。
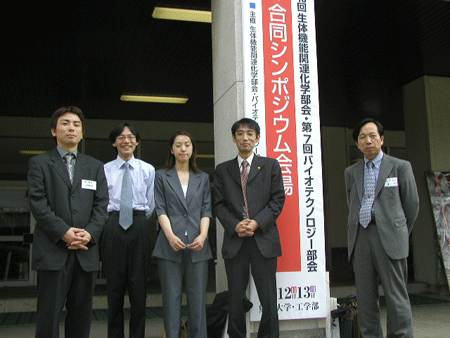
学会での一こま(右より寺前教授,西沢講師,石井修士,私,吉本博士)
日本化学会第84回春季年会学生講演賞および青葉理学振興会黒田チカ賞を受賞して

古屋亜理
この度、日本化学会第84回春季年会学生講演賞および青葉理学振興会黒田チカ賞を頂くことができました。
私は平成9年に東北大学理学部化学科に入学し、学部3年の後期から現在の所属である理論化学研究室に配属となりました。その後、研究活動は助教授である美齊津文典先生のもとで行うことが決定しました。配属されてすぐに教授である大野公一先生と面談をしたとき、先生は私に「趣味は何か?」と質問されました。先生はおそらく体を動かすスポーツか料理や裁縫などという答えを予想し、そこから研究生活と関連づけて話をしようと考えていらしたのではないかと思いますが、私は何も考えずに「買い物です」と答え、先生を絶句させてしまったことをよく覚えています。また、将来はどう考えているかという質問に対しても、研究が面白くなれば大学院に進学したいがそうでなければ企業への就職を考えていると答えました。あれから5年の月日がたち私は大学院へ進学し、上記のような賞を頂くことができました。これもひとえに大野先生や美齊津先生、理論化学研究室のスタッフや先輩、同輩および後輩の皆様のお力添えがあったからこそ成し遂げられたものであると心から感謝いたしております。
私は研究室への配属後から金属原子と分子からなるクラスターの研究を行っています。クラスターとは2〜数100個程度集まったものであり、原子・分子と固体あるいは液体との中間の物質と定義されます。クラスター研究は(1)凝縮相の微視的モデル、(2)クラスター特有の新規な反応や機能性物質の開拓および(3)反応中間体としての観点か数多く行われています。日本化学会第84回春季年会学生講演賞で受賞対象となった研究は、「Mg+-CH3X (X=I, Br, Cl)錯体のレーザー光誘起解離における解離イオンの放出角度分布」です。青葉理学振興会黒田チカ賞の方は「マグネシウム一価イオンと分子からなるクラスターの電子励起状態および光誘起解離過程」です。これらは、大学院に進学してから始めた研究で、光解離分光を用いて金属イオン(M+)と分子(L)からなるクラスターM+Ln (nは分子Lの数)の電子励起状態と電子励起状態からの解離過程に関する知見を得ようという研究です。実際に研究を行った系はマグネシウム一価イオン(Mg+)とアクリロニトリル(CH2=CHCN; AN)およびヨウ化メチル(CH3I)からなるクラスター Mg+(AN)n, Mg+CH3Iです。反射型飛行時間質量分析計を用いて、これらのクラスターを質量選別した後、解離用レーザーを照射して生成した解離イオンを質量選別して観測しました。Mg+(AN)nクラスターでは、AN分子数の増加に伴い電子励起状態のエネルギー順位のシフトが観測され、これはクラスターの構造に起因することが分かりました。一方、Mg+CH3Iでは、解離イオンとして単純なヨウ化メチル分子の脱離によって生成したMg+に加えて、正電荷がマグネシウムからヨウ化メチル分子へ移動したCH3I+、分子内結合の解離によって生成したMgI+などの複数の解離イオンが観測されました。そこで、この様な解離のダイナミクスに関する情報を得るために解離イオン飛行時間分布の解離光偏光方向依存性を測定した結果、CH3I+とMgI+において顕著な異方性が観測されました。観測された解離イオンの放出角度分布は、金属原子に局在した電子遷移と基底状態におけるMg+CH3Iクラスターの安定構造によって説明できることが分かりました。この様な研究活動を展開するにあたり、美齊津先生には実験装置に関する技術的なことから、学問的なことに至るまで様々な面で指導していただきました。また、大野先生には研究内容に関する指導に加え、研究に対する姿勢というものも教えていただきました。先生の御指導から、勉強と研究の違いを知ると同時に、自分の課題を知ることができました。この場を借りて改めてお礼申し上げたいと思います。
最後になりましたが、この様な機会を与えてくださった東北化学同窓会の皆様にお礼申し上げるとともに、本同窓会の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。
青葉理学振興会奨励賞を受賞して
理学部 化学科 廣瀬 剛史
まず、はじめに今回このような賞を受賞させていただいたことに感謝の意を表したいと思います。
正直なことを申し上げますと、なぜ自分がこのような賞を受賞できたのか不思議でした。基本的に授業だけを聞いて、宿題以外の時間外学習を殆どしなかったからです。しかし、よく考えるとそれは、東北大学理学部化学科の授業を担当されている先生方の教え方が良かったからであるという結論に達しました。そして、自分が素晴らしい環境で勉学に勤しむことができたことに感謝しなければならないと思いました。
受賞したときのことを少し書かせていただきますと、青葉理学振興会奨励賞と共に、金一封をいただきまして、思わぬ収入が入ったことに気持ちが高揚し、その日のうちに自分の所属する音楽サークルの人たちと一緒に夕食を食べに行き、おごったという思い出があります。残りのお金は、趣味の音楽に使いつつ、賞の趣旨を考えて、研究をするために必要な分野の本を購入するなどに当てたりしながら全部使ってしまい、結局貯蓄にはまわす事はしませんでした。
さて、先ほど研究に必要な本を購入したと言いましたので、ここで今自分の行っている研究について書かせていただきたいと思います。ご存知の通り、化学科は3年生の後期から研究室に配属され、1年半その研究室で卒業論文に向けた研究を行って行きます。自分は、昨年の10月より理論化学研究室に配属され、大野先生の下で研究を行っています。研究のテーマは、ポテンシャルエネルギー曲面上の反応経路の完全探索です。と言われても、という方のために説明させていただきたいと思います。
分子の電子状態のエネルギー(エネルギー期待値)は分子内の原子核配置(分子の構造)によって異なり、全ての原子配置を考えると、エネルギー値はある曲面を構築します。この曲面をポテンシャルエネルギー曲面(Potential Energy Surface : PES)といいます。また、われわれが普段扱っている分子構造は安定構造(Equilibrium Structure : EQ)と呼ばれ、PES上ではEQはその極小点であり、また反応の障壁という山の峠に存在する遷移状態(Transition State : TS)は1次の按点であります。化学現象を理解する上で、これらEQ, TSを求めることは重要であります。これらは、PESを全空間に対して求めることにより全て見つけることは可能となりますが、原子がN個の分子では、PESは3N-6次元の関数となり、それを行うことができるのはせいぜい3原子分子程度であると言えます。そこで、さらに大きな分子を扱うにあたり効率的にEQ, TSさらに解離反応の反応経路(Dissociation Channel : DC)を求める方法が必要となります。本研究室では、それを実現する超球面探索法を開発しました。超球面探索法とは、EQの近傍のPESはほぼ調和的であるのですが、反応経路の存在する方向ではエネルギー値は調和近似の値よりも低くなっているという仮定の下に、調和近似における等エネルギー面曲面を作る超楕円面をスケールして超球面にし、その超球面上でのエネルギーの極小点を見つけ、超球面を広げながら極小点を追跡していくことで反応経路を求めていきます。反応経路が山の頂上に達したらそこがTSとなります。TSから反対の方向に反応経路を下れば新しいEQに到達できます。こうしてこれを繰り返すことによりすべてのEQ, TS, DCを求めることができる方法であります。自分はこの方法をいろいろな分子に適用し、EQ, TSを求め、それらをつなぐ反応経路を求めることによって、分子が反応でどのような形をとって変化していくのかを調べています。
今回、学業成績に対して表彰されたわけですが、今後はよい研究を行って研究の分野で評価されるように努めたいと思います。