雑感
三上 直彦
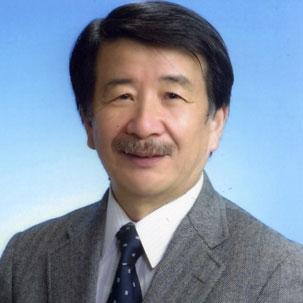
平成18年3月末をもって停年退職いたしましたが、ふり返れば、昭和36年本学部入学、同40年大学院進学、同44年(1969)助手採用以来、教官-教員として37年、学生時代を含めると実に45年の永きに亘り理学部・理学研究科・化学教室の多くの本同窓会会員、教職員、学生諸氏のお世話になりました。この機会を拝借して、これまでに皆様から頂いたご厚誼に深く感謝申し上げます。現在は、継続中の科研費(特別推進研究)の関係で、理学研究科客員教授というありがたい環境を戴いて、物理A棟4階の一室におります。ただし、ボランティアとして新入生の講義を受け持っており、研究活動はこれまで同様ですので、現役時と大差ない日常を過ごしておりますが、諸会議出席が不要になったことが停年後の最大のメリットとして、大いに享受いたしております。
さて、この度、東北化学同窓会から退職に際して何か書くようにとの依頼を拝して、この十数年間の大学における教育・研究・運営等に関わる状況変遷の背景を、私なりの独断と偏見で振り返って見ることにしました。
昭和から平成に年号が変わるころ、全国の国立大学の諸設備が劣悪・老朽であることがしばしば報道され、バブル経済絶頂期にあった民間企業と比較して余りにも脆弱な大学のインフラ整備拡充が喧伝されていました。当時の大手民間企業は、海外にも基礎研究部門を設立するなど、米国IBM基礎研やBell研究所に匹敵する先端科学推進の意欲を誇り、日本化学会は経済産業界の要求に呼応して博士号取得者数の大幅増大を提言、文部省は博士研究員制度整備拡充などで我国企業の独自技術開発推進の後ろ盾になっていました。その後、平成4〜5年のバブル崩壊とともに、多くの企業は合理化・経費節減による経営体質改革を進め、不急不要の基礎研究部門は真っ先に消滅廃止の道をたどり、国内外の基礎研究所・中央研究所の多くの優秀な人材は配置転換か転職を余儀なくされることになりました。その頃から大学の研究内容にアカウンタビリティの要求が声高に叫ばれ、税金でまかなわれている大学が国の産業基盤研究の役割分担を果たすべきであるという、企業の論理が社会通念になっていきました。
平成5年、ゼネコン疑惑で行き先を失った建設省関連予算は文部省所轄事業に振り向けられたので、大学関係建築設備予算はバブル崩壊の経済産業界とは逆の位相関係で急速増大しました。更に、平成7年の科学技術基本法制定によって科学技術立国を標榜して、国債を財源とする“未来開拓学術研究推進事業”等の新規科学技術研究事業が創設されたので、財政再建を求められている緊縮型国家予算とは逆に、大学関係建築設備・先端科学研究費等は特異的な伸び率となりました。しかし、その代償として、大蔵省は文部省に対して従来型のばら撒き方式の見直しを要求し、平成12年の省庁再編に合わせて設立した総合科学技術会議の基本方針の下に重点配分や評価査定の主導権を掌握して、予算増大の説明責任をとるという構図が出来上がったわけです。その結果、大学・研究関係のあらゆる制度改革や機構再編は文科省・財務省主導型になり、大学・研究機関の“ボトムアップ”型の企画提案は一蹴され、多くの大学教育研究者は中期計画策定や数値目標設定など空々しいトップダウン型の下請け作業に携わり、膨大な時間と労力を割かれることになりました。一方、国家基本方針として「行政改革」を掲げている政府は全省庁の公務員定員一律削減を推し進め、科学技術先進国として一層の高等教育強化が求められているにも拘らず、大学教職員数も着実に定員削減が実施されましたので、各大学は組織・機構の再編成を繰返して生残り作業に追われることになりました。
私の教授在任中は、まさしく上記の構造転換の奔流が渦巻いていた年代であり、文科省出先機関の一公務員として次々と舞い降りてくるトップダウン型制度変革、平成4年教養部廃止、平成7年大学院重点化、平成13年独立法人化等、への対応作業に追われておりました。その間に行われた教育プログラム改編=早期専門教育、セメスター制度の形式的導入、卒業必要単位数減、理科実験単位減、在学延長年限減、受講科目数制限案等は、各種委員会委員の誠実な対応にも関わらず、敢えて極言すれば、全てが定員削減に起因する多くの歪みへの対処療法として導入された変革であり、本来の教育改善計画の一環として発想されたものでないことは明白であると言わざるを得ません。同様な作業に携わった全国の教育・研究者・事務職員の労力に鑑みると、その努力に相応しい教育改善効果が得られるかどうか大きな疑念があります。
実際、私が過去20年間に関与した研究費総額は優に数億円を超え、莫大な血税による研究支援のもとに自由な研究活動を展開させて戴きました。しかしながら、私の在任期間中に発生した数々の制度改編の激流に対処することに終始しただけで、その支援に相応しい本来の教育研究運営制度の構築に向けた十分な努力が出来ないまま停年を迎えてしまったことは大いに反省するところです。
かつての大学が“自治”の名のもとに百年一日のごとき小田原評定を繰り返して、世間から当事者能力を疑われた歴史がありますが、現在のようなグローバリゼーションの仮面をかむった経済至上主義による諸制度改編は、大学を単なる高等職業訓練機関に変えるだけであり、成熟社会における「アカデミア=智恵の拠点」として、世界をリードする高等教育研究拠点に変革することには寄与しないでしょう。一方、動きが速い経済産業界では、単なる米国亜流の制度導入に終始する改編や過去十数年実施してきた一元的な競争・効率・評価方式を見直し、逆に長期的展望の研究開発投資を増やし始め、大学の社会的役割に対する認識が変化している兆候もすでに現れております。現在の大学はこのような社会状況の先端趨勢とは再び半周遅れで、表面的市場経済原理による教育制度変革を始めようとしている有様です。このような脆弱な改革を諸大学や先端的大学院が続行していると、我国の人口減少が際立ってくる10年後には中国、インドに抜き去られる結末は明らかです。
理学部・理学研究科は、拙速な経済原理の尺度では計測できない「智の創出に携わる教育研究」の存在意義を社会に対して説得し続けるべきであり、大学のアカデミアの旗手として、我国の歴史的背景、社会構造、産業構造、自然環境の実情を見通した総合的視点による自立的変革を先導する役割を果たすであろう、と期待しております。アカデミアとポリティクスとの理不尽な軋轢はいつの世にも存在することですが、教育は国家百年の盛衰を左右する大事であることを鑑みると、私の心配が単なる老婆心、杞憂に終わることを切に願って、同窓生各位におかれましても、今後の大学教育・研究制度改編の推移を注意深く見守っていただくことを願っております。
(平成18年7月末)
三上直彦先生のご停年によせて
藤井 朱鳥
平成18年3月末日に三上直彦先生がご停年を迎えられました。三上先生は昭和36年に東北大学理学部にご入学以来、助手、助教授、教授と東北大学化学教室一筋に歩まれました。助手時代の2光子蛍光励起に始まり、助教授時代のパルス超音速ジェット法開発、そして教授時代のクラスター赤外分光の開拓と常に分子分光学を新たな潮流へと導く業績を挙げられ、仙台が分子分光学の一大拠点として世界に知られる原動力となってこられました。
また三上先生はその暖かみのある魅力的なお人柄でも知られ、多くの学生に卒業後も永く慕われ続けています。最終講義と引き続いて行われた同窓会が、平日木曜日という日程にも関わらず、多くの同窓生で非常な盛況となったことはまだ記憶に新しいところです。先日には三上先生のご停年を記念して国際シンポジウムが開催されましたが、文字通り世界中から主だった分子クラスター研究者が集まり、あたかも分野の最高峰の国際研究集会であるGordon会議が仙台に引っ越してきたかのような会となりました。参加した各国研究者による心のこもったスピーチは、三上先生が単なる科学的な業績を越えて友人として世界の研究者から深く敬愛されていることを強く印象づけるものでした。なお、この会で世界のクラスター分光学者一同から三上先生へ、日本酒及び温泉学博士号が贈られたことをご報告しておきたいと思います。
と、ここまでは過去形で記しましたが、実は三上先生はまだ現役の研究者としてご活躍を続けています。近年の大学機構改革により、停年後も研究費の続く限り大学に籍を置いての研究活動継続が可能となりました。三上先生も居室を物理棟に移し、名誉教授研究室を主催されています。ご自身にとっても新領域になるテラヘルツ波の応用や超高感度FTIR分光器の開発など、年齢を全く感じさせない新たな発想の具体化に精力的に取り組んでおられます。超高感度FTIR分光器開発の主目的のひとつは水−アルコールなどの混合水素結合系の構造解析ですが、そのサンプルとして熟成された各種の水和エタノールの収集も着々と進んでいると伺っています。「なぜか測定前にサンプルが減っていく」という話も同時にお聞きしましたが、これは三上先生が何よりもまず自分で確かめるという科学者としての態度を貫徹されていることによるものであると思います。三上先生は玄人はだしの腕前を誇られる釣りや料理、そして最近は日本古代史の研究と多彩な趣味をもつお方ですが、もうしばらくは研究生活を続けられ、後進の我々に分子分光学の今後の方向性を更に示して頂けることを願って止みません。